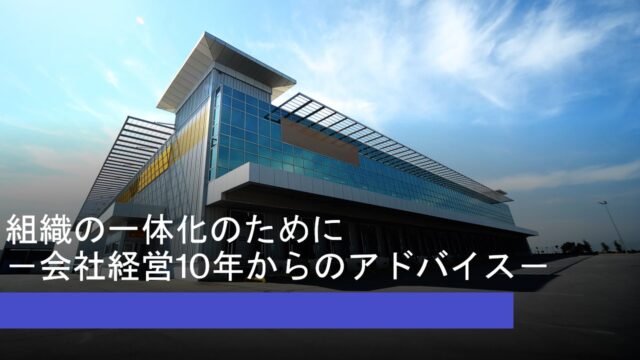どうせ会社で働くからには、自分の力を思い切り発揮でき、一つの仕事を終えたときに達成感を感じたいものです。
そのための条件として、いくつかあると思いますが、私の経験では、上司の役割が大きな比重を占めているのではと思っています。
それでは、社員がそのような高揚感を意識し、行動する理想の上司とはどんな人なのでしょうか。
ぐんぐん引っ張ってくれる親分肌がよいのか、細かいところまで指導してくれる上司がよいのか。
DeNA会長の南場智子氏は、その作品「不格好経営」のなかで理想の上司について、いくつかの事例を紹介しています。
私も、このような人のもとでなら、しっかりついていきたいと思った上司もいれば、反面教師の見本としたい上司もいました。
今回は、南場氏の作品と私の経験から「社員をわくわくさせる理想の上司」について紹介します。
理想のリーダーになるための努力
理想のリーダーになるためには、自分が組織のトップとしてリードする中で、失敗を繰り返しながらも、その秘訣を掴んでいくことが大切のようです。
DeNA会長の南場氏は、そのことを裏付ける事例をその著作のなかで紹介しています。
20代の若手社員をある営業チームのトップに据えたときに、そのリーダーがいろいろ苦労を重ねる中で、リーダーとして成長していく姿を、南場氏はその作品のなかで紹介しています。
赤川は、一生懸命自分のやり方をチームに広げようと頑張ったが、チームがまったく機能しなくなってしまった。
大手広告代理店から転職してきたメンバーなどもいて、年下の素人に従うのは釈然としない部分もあったのだろう。赤川がリーダーになってからメンバーの業績の未達が続いた。
数字は上がらないし、赤川はさらに細くなるし、この人事はちょっと無理があったのではと懸念の声も上がったが、これこそ絶好の成長の機会と思い、そのまま様子を見ることにした。
成果が出ない赤川はミーティングの頻度を増やし、ほかのメンバーにいろいろ教えようとしていたが、どんどんチームの気持ちは離れ、「崩壊寸前」という言葉まで聞こえた。
あるとき赤川は、パタリと指示をやめてしまう。このままでは全社の業績に大きな影響が出てしまう、何とか自分一人でチームの未達分を補おうと、外での営業にもう一度軸足を戻したのだ。
日中は全部外出。夜も多くは営業にあて、チームの誰よりも足を使って成果を上げた。会社に戻ってからは提案書や営業アプローチを資料に残し、ほかのメンバーからも自由にみえるように可視化した。
そして赤川はチームに言った。自分はよいリーダーになれず苦しんでいる。助けてくれ、と。
そのひたむきさがチームの心を打っていった。
一人、また一人と赤川を助け始め、半年後にはDeNAで、1,2を争う結束の強いチームに仕上がった。
この経験で赤川は、彼なりのマネジメントスタンスを見つけたのではないかと思う。誰よりも働く、教えるよりも見せる、上から目線でなく、自分をさらけ出して一緒に戦うスタイルだ。なかなか頼もしいマネージャーへと育っていった。
(南場智子著 不格好経営)
この事例は、若いリーダーが苦労する中で、リーダーとしての素質を開花していく姿を示しています。
リーダーの素質
前項では、理想のリーダーがいかに育つかについてひとつの事例を紹介しました。
ここでは、プロジェクトもしくは会社を引っ張っていくリーダーに求めらる素質について事例を紹介します。
私がダムの建設現場で働いていた昭和50年代は、ダムという構造物を造るために、リーダーは必要の技術力を持ち、ぐいぐい部下を引っ張り、叱ってでもやるべきことをやらせるぐらいの胆力をもったリーダーが多かった気がしています。
しかし、現在のように一つのプロジェクトを成し遂げるために必要となる技術が複雑を極め、さらに、そこで働くメンバーのやりがいを感じさせていくためには、私が技術屋として育った頃とは、異なったリーダーの素養が求められていると思います。
この点については、DeNAの創立から南場氏を助け、南場氏が社長を退いた後に社長となった守安氏に対する南場氏の評価が参考になると思います。
(守安は、創業期の、1999年に日本オラクルからほかの5人と一緒に入社してきた。見た目は生意気なガキで実際生意気だった。
———-最初はシステムエンジニアの一員として活躍し、いつも期待以上の成果を出していたが、ただものではないと感じ始めたのは2001年初め頃だった。
———-そのころからただものではないと感じ、それ以来私は、次々とこれでもか、と難しく、重たい仕事を守安に任せた。守安は、任されたミッションに加え、経営に的確な「文句」を言い、そのつど、指摘したからには解決するまでやり切った)
私は賢い人が集まるとされるコンサルティング会社時代を含め幾人もの天才、秀才を見てきたが、その私が驚くほど数字と論理に強くビジネスセンスにも長けていた。
そして部門を統率できるブレなさ、強さがある。人格は、責任感が強くフェア。権威におもねることがない。そして約束を守る。
長年一緒に仕事をして私は守安から多くのことを学んだが、その中で一番尊いことは、自分の利益や感情とものごとの善し悪しの判断を決して混同しない清々しさだ。守安が新米のときからトップになるまで見てきたが、一時たりともそこに曇りを感じたことはない。
一見傲慢で、実際生意気だが、実は謙虚でよく学ぶ。そして、どことなくいびつなところがチャーミングで、愛されるというのも経営トップとして大きなポイントだった。
(南場智子著 不格好経営)
責任を取る上司
理想の上司としてあげられる特徴として、責任の取り方に部下の厳しい視線が向くようです。
堂場修一氏はその作品「沃野の刑事」で、将来責任を問われる事態が想定されるような事態に遭遇した際の上司が示した姿に感動を覚えた部下の話を書いています。
ある疑獄事件に絡んで、商社の若手サラリーマンが遺書を残して自殺しました。
この自殺に絡んだ遺書を見つけた警視庁捜査一課の高峰理事官は、この件を警察が公表するかどうか、上司の佐々木捜査一課課長に相談を持ち掛けます。
相談を受けた課長は、自殺を公表する立場には捜査一課は関係ないこと、そして普通の人の自殺については公表しない慣例をもとに公表しないとの判断を下します。
ここで紹介する一節は、その際の理事官と上司である課長との会話です。
政治家の秘書は公的な人間だが、今回勝手に一般人と解釈したのだろう。「普通の人の自殺は広報しない」という原則を盾に、マスコミの取材は遮断できる——問題は、遺書の存在がばれた時だ。その件を指摘すると、佐々木は平然と答えた。
「遺書の件は、警視庁の捜査には何も関係ない。地検特捜部には関係するかもしれないが、捜査一課と特捜部は、仕事上でまったく関係していない」
何という胆力か‐———佐々木は無難なタイプの上司であるが、いざという時には腹をくくる。
すぐ下で支えてきた高峰は、何度もそういう場面を見てきた。ある意味理想の上司——「上司は責任をとるためだけに存在する」という言葉が昔からあるが、実際にそんな風に仕事をしている上司はまずいない。佐々木は数少ない例外だろう。
(堂場瞬一著 沃野の刑事)
強すぎるリーダーの弊害
ダム建設に従事していたときの経験です。
ダム建設も後半に入り、追加的な付帯設備を構築する必要があり、工期的にも短期間に工事を終わらせる必要がありました。
私の直属の上司であった所長は、技術力があり、また、判断力にも優れた人でした。短期に設計を終わらせ、さらに施工も行うということで、所長もその業務にかなり力が入っている様子でした。
設計は部下である我々若手の技術屋が行っていましたが、その設計を持っていくと必ず、見直しの意見が出、結局、所長の意見のままに仕上げることが多くなりました。
部下に任せるというより、まずたたき台を作らせ、そこに所長の考えを盛り込んでいくといったことで仕事が進んで行きました。
そのようなことが続いていくと、我々も、最後は所長が決めるのだからという意識が働くようになり、所長が何を言うかに気を向かわせることが多くなりました。
そのときは、物事が迅速に決まっていくこともあり、こういう状態が必要なのだと思っていました。
しかし、いざダムに水を貯め始めると、トラブルが発生し、短期間に設計した付帯構造物の一部でトラブルが発生し、補修工事をせざるを得ない状況となりました。
トラブルが起こったところは、私が設計を担当した箇所でした。設計当初は、一部基礎に不安な箇所が存在していましたが、所長の了解を取ってあるのだから問題ないだろうとして処理した箇所でした。
トラブルが発生したときには、あのときに、今少し調査を進め、いくら所長が強いひとであっても意見を交わし、設計に望めばよかったと反省した経験でした。
組織のトップが強い人で、自らなんでも決めていくといった組織では、なかなかに所長と意見を交わすことができなくなり、部下は受動的な姿勢でしか仕事ができなくなってしまうようです。
この反省から、自分がトップに立った時には、独断専行はやめ、まずは周りの意見を聞き、その上で部下の納得感を確認したうえで判断し、後は任せることにしました。
部下のやる気が向上し、能動的な行動が目立つようになり、自分のとった行動の正しさを感じた経験でした。
あとがき
理想の上司について、南場氏と堂場氏の作品および私の経験からいくつかの事例を紹介しました。
これらの事例から、理想の上司が持つ特性としては、次の5点が挙げられると思います。
- 上から目線ではなく、また、独断専行的な行動を取らず、周囲の意見を聞ける上司
- 自分の利益や感情とものごとの善し悪しの判断を混同せず清々しさを持つ
- 謙虚でよく学ぶ
- いざという時に責任をとる
- ふとした行動にチャーミングがあり愛される
ぜひ、このブログを読んだ皆さんも、理想の上司となり、組織が活性化し、わくわく感を持って部下が働ける組織を作ってもらえればと思っています。