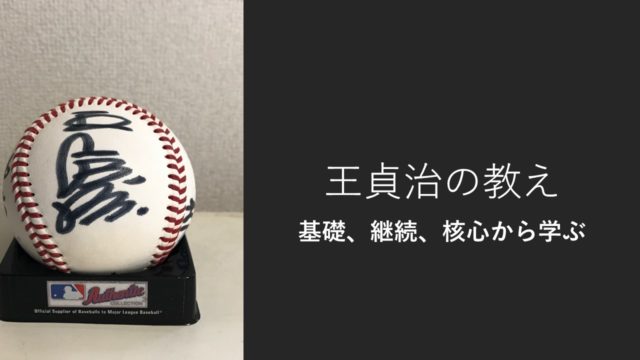今回は、話題を変えてお送りします。
2020年は、台風15号、19号、さらに豪雨をもたらした低気圧の襲来で、各地で甚大な災害が発生しました。
土木工学を学んだものとして、被災した地域の様子を見、改めて自然の驚異、そして自然の持つ力の強大さについて考えさせられています。
毎年どこかで発生する自然災害もそうですが、トンネルなどの土木構造物を建設するときも、自然の力が人の能力を超えて襲い掛かり、大きな災害になることがあります。
作家、吉村氏は、丹奈トンネルの建設の著述で、人が自然に挑戦したときの潜在的な恐ろしさを克明に書き表しています。
私も、水を貯める構造物の建設に携わったときに、自然のこわさを味わった一人です。そのときに、自然に対し謙虚な姿勢で対峙することが大切であることを学びました。
今回は、吉村昭氏と私のダム建設での経験から、「自然の怖さと構造物を構築するときに技術者はどのように自然に向き合うべきか」について紹介します。
人の挑戦をはねのける自然の力
小説「闇を裂く道」の舞台は、大正7年に着工され、15年11か月の月日を要し、従事した工夫、作業員の延べ人数が250万人を数えた丹奈トンネルの建設現場です。
着工から2年が経ち、トンネルの掘削もほぼ順調に進んでいたときに、崩落事故が起こりました。
結局、13名が崩れた岩石の下に入り圧死し、17名が6日間の救援作業の後に救助されました。
崩落事故が発生し、すぐに鉄道院の富田建設所長はじめとした調査団がトンネルの中に入り、事故現場に向かいました。
まだ、崩落が続くトンネル内で、富田所長は自然の力の強大さに、改めて恐怖を感じるのでした。
ここで紹介する一節は、まだ、崩落が続くトンネル内で、富田所長が自然の力の強大さに改めて恐怖を感じたときの場面です。
“坑口から二百八十メートルほど進んだ時、突然、岩石の崩れ落ちる音がとどろき、かれらは、おびえたように足をとめ、後ろへ退いた。
—–土圧をささえた支保工のきしむ音が、前方でしきりにきこえていた。
富田たちは、しばらくその場で身じろぎもせず立っていた。—–トンネルを掘ることは、人間の生活をより便利にするための行為だが、大自然に対する挑戦であることに変わりはない。
それまで維持されてきた地中の秩序が、それによって激しくかきみだされる。
工事関係者は、そのことを十分に知っていて、謙虚な態度で一筋の道をうがってゆく。
—————
このようなつつましい仕方でトンネルを掘り進んできたのだが、崩壊事故が起こったのは、大自然の怒りが爆発したことをしめしている。
わずか一時間三十分前に、専門の技術者たちが点検して全く異常がないと判断した箇所が、突然、崩落したことは、大自然が、人智でははかり知れぬものを秘めているからにほかならない”
(吉村 昭著 闇を裂く道)
自然に挑戦するために必要な謙虚さ
崩落に伴ってトンネル深部に閉じ込められた人々を救助すべく、直ちに救助抗が3本掘られ始めました。
崩落した岩石や山を支えていた支保工用の丸太材などが障害となり、救助抗の掘削は遅々として進みませんでした。
そのような状況を前に、鉄道院の富田所長は、トンネル屋が背負う危険の大きさを改めて思うのでした。
ここで紹介する一節も、救助が遅々として進まない状況を前に、鉄道院の富田所長が、改めて感じた、トンネル屋が背負う危険の大きさです。
“トンネル屋という言葉が、胸に湧いた。
山に人工の穴をうがつのは自然の秩序を乱すことであり、トンネル工事に従事する者は絶えず崩落事故を予想しなければならない。
それを避けるために些細な物音、空気の動きに細心の注意をはらう。
妻が出産した折には一週間構内に入らぬ習わしがあり、女が抗内に入るのをかたく禁じる現場もある。
それは、山の神―-女神の嫉妬を買い、山が荒れるからだという。迷信だと言って笑うのは容易だが、それほど神経を使わなければならぬ危険な職場だ。
そのような注意をはらいつづけていても、事故は起こり、現実に眼前の崩壊現場では死体が発掘され、多くの者が絶望視されている。
トンネル屋とは、常に死を覚悟しての職業と言ってもいい”
(吉村 昭著 闇を裂く道)
弱点を徹底的についてくる水の力
丹奈トンネルほどの大規模構造物ではありませんが、私も、水を貯める構造物の建設に携わったときに水のこわさを経験しました。
水を貯めるために土を盛り上げて池の基盤層を形作り、その表面に水を止める遮水材を張りつけて人工池を構築する工事でした。
池が完成し、水を貯め始めてしばらくたち、水位もかなり上がったときに、池から水が漏れていることが観測されました。
早速、損傷した箇所を修理するため、水を抜き、その部分の遮水材も撤去し、水が漏れた原因をさぐりました。
遮水材の一部に傷がついており、そこから水が漏れたことがわかりました。
さらに、その個所の基盤層を調べていくと、モグラ穴といわれる、直径10センチメートルのトンネルが形成されていました。
わずかの水の染み出しが、長い時間をかけて周りの土を少しずつ洗い流し続けました。
ついには、径が10センチメートルほどのパイプを形成し、大量の水を流し、その力で基盤層を破壊したものでした。
学生時代に堤防で起きる事故として、堤防内に浸透した水が徐々に堤防の盛り土部分を侵食し、ついには堤防の破壊にいたるパイピング現象というものを学びました。
そのときはそんなこともあるのだなと思っただけでした。
しかし、実際にパイピング現象が起きている現場を目の前に見たときは、まったく違っていました。
わずかな弱点でも、そこを狙い撃ちにし、徐々に傷を広げてしまう力を水が持っていることに、改めて恐ろしさを感じました。
技術はどのように自然に向き合うべきか
大学で土木工学を学んだときに、土木構造物が、風や水といった自然の力で破壊する事例もいくつか勉強しました。
ただし、教科書で起こったことは他人事であり、自分のこととしてとらえることができませんでした。
しかし、自分が設計した構造物が、水の力で損傷を受ける事態に出会ったことで、そこから多くのことを学びました。
まず水の力についてです。
普段見る川の水は静かに流れ、一つの風景を作っており、場所によっては、観光資源になることもあります。
しかし、いったん、水に対抗して物を作る段になると、水はその性質を急に変え、人の能力をあざ笑うかのような行動に出ます。
「水に抵抗して構造物をつくるときには、水の気持ちになることが大切」といった、大先輩の言葉を思い出します。
また、水をはじめ、自然は弱いところを確実に狙ってきます。
そういった意味で、自然に対抗しようとするときは、つねに謙虚な気持ちで取り組む必要があると思っています。
自分が設計した構造物について、あれだけ安全性をもって設計したのだから、何も起こるはずがないと、高をくくっていたのも事実です。
そのために、弱点になりそうなところに十分な目がいかないうちに構造物が出来上がりました。
ところが、水を貯め始めてから、弱点として自分が十分に注意をはらわなかったところで事故が発生し、ひどく反省したことを覚えています。
これも上司からの言葉です。「自然に対しては、徹底的に謙虚であること」。この言葉をすっかり忘れた経験でした。
まとめ
自然の災害や人工的な構造物の損壊から多くのことをいつも学びます。
しかし、それが自分事でないことで、つい、自然に甘えてしまうのが我々ではないでしょうか。
「自然に対するときには徹底的に謙虚になれ」といった先輩の言葉を常に、持ち続ける必要があると思っています。