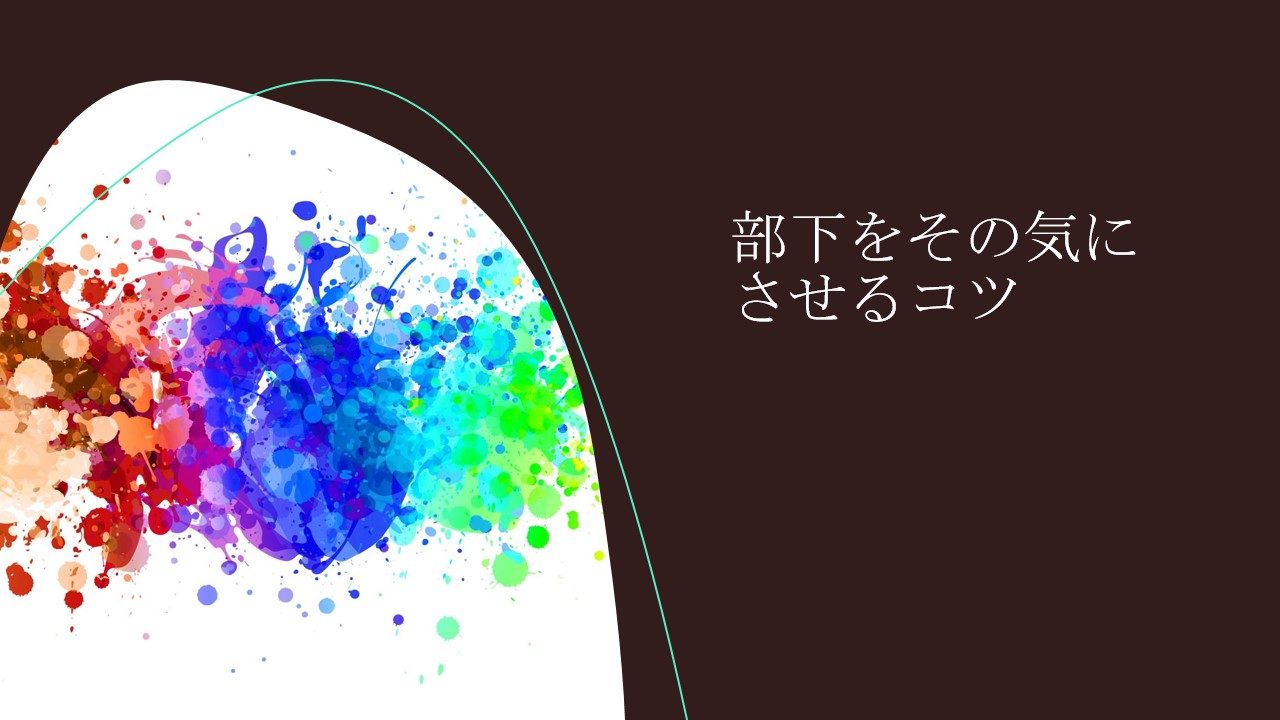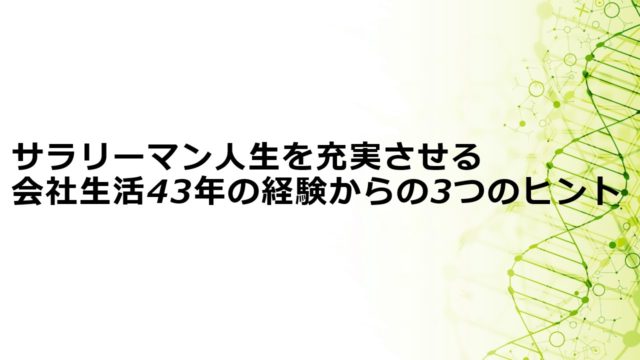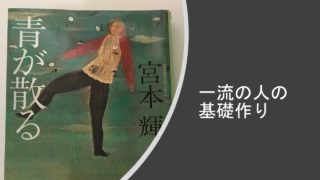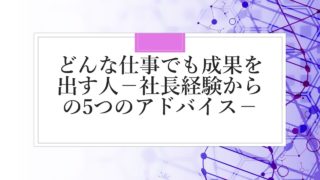会社など、一つの目的に向かって組織として仕事を進めるときに、部下の力を最大限に生かして成果を出すためにはどうすればよいのでしょうか。
その手立てはいろいろあるかと思いますが、今回は、「部下を信用する」と「働く意欲を駆り立てる」の2点について紹介します。
作家、上田秀人氏は、その作品の中で、この2点について、歴史上の人物の行動を事例とした小説を書いています。
私も、長い会社生活の中で、担当から社長まで経験しましたが、その中で、上司として、部下とともに仕事を成し遂げていく過程の中で、この2点の重要さを学びました。
部下を信用する上司に人は集まる
上田秀人氏の長編時代小説「勘定吟味役異聞」シリーズは、18世紀初めの江戸幕府が舞台です。
兄の急逝で、急遽、水木家の家督を継いだ主人公、聡四郎は、能力のある部下を持たず、しかも幕府内での権威を得ようとする新井白石の引きで、勘定奉行の次席となる勘定吟味役に抜擢されました。
剣の腕は一流のものをもちながら、勘定関連の仕事には疎い聡四郎でしたが、持ち前の誠実さと謀を嫌う性格から、新井白石に命ぜられる、将軍家の跡取りに関わる難題を、ひとつ、ひとつ解決していきます。
シリーズ第五巻の「地の業火」では、第八代将軍を狙っていた、徳川三家の一つである尾張家の当主吉通が急死したところから話が始まります。
吉通の死の真相を探るよう新井白石に命じられた聡四郎は、幕府内で展開される策謀の中で、ただ一人の部下と偶然に聡四郎の後見人となった大店相模屋の主人、伝兵衛知の支援を得て、その真相に迫っていきます。
新井白石は、命じられたことを確実に処理する聡四郎の能力を理解してはいましたが、その性格から、まったく聡史郎を信用しようとしませんでした。
部下がやることだけやれば、あとは自分だけで処理してしまおうとする、そのような新井白石の態度に、聡四郎も白石に従うことに疑問を感じるようになりました。
ここで紹介する一節は、聡四郎が、そのような思いにとらわれていることを理解する相模屋伝兵衛が、新井白石に関して、上司としての資質に関して語る場面です。
(伝兵衛)「増上寺の一件以来、水城さまは新井さまにうとまれておられる」
(聡四郎)「さようでござる」
少し前、新井白石に命じられて聡四郎は間部越前守の失策を探った。
そして聡四郎は間部越前守と増上寺がかわした将軍菩提寺選定にかかわる密約、その証を手に入れた。密約は、七代将軍傳育(ふいく)を盾に幕府最高の権力を握った間部越前守を一気に追い落とすだけの内容を示していた。
六代家宣の生死にかかわる密約を記した書付を、聡四郎はあってはならぬものとして独断で焼却し、新井白石には写ししか渡さなかった。
「あのおりにも、少し感じておりましたが、新井さまは、人を信用なさりませぬ。なんでも己で対処し、他人のやることはいっさい認められない」
「―――――」
無言で聡四郎はうなずいた。
「それじゃあ、だれも味方をしてくれない」
紅( 伝兵衛の娘、聡四郎の許嫁)があきれた
優れた儒家として、6代将軍の信望の厚かった新井白石でしたが、部下を信用しないという性癖から、部下に疎まれる存在だったようです。
部下を信頼して事業を立ち上げ
私が40代のころ、所属する部門で新たに海外コンサルティング事業を展開することになり、そのリーダーにつきました。
それまで、海外を対象にした事業はその部署では皆無であったことから、一からのスタートでした。
まずは、メンバーを集めようということで、東京の本社をはじめ地方の事務所を訪問し、事業の立ち上げの理由、今後の見通しなどを話して回りました。
部門の将来の成長に不安を感じていた20代後半から30代の若手社員が、海外に新たなビジネスの機会をとらえようということで、10名ほどが集まりました。
私自身、海外でコンサルティングを行うことについての経験はゼロであり、海外で事業を進める会社に指導を受けたり、共同で行える案件づくりなどを協議したりしてきました。
また、集まったメンバーと議論を進め、その後の展開を考え、目標を決め、当面の方策を決めました。
集まったメンバーは、意識が高く、やる気もあり、私が細かいところまで指示を出すことは、メンバーのやる気を削ぐと考え、方針に則って自由な発想で仕事を進めてもらいました。
あえて言えば、メンバーを信頼し、それぞれの行動力を信じて、事業の立ち上げを図ったと言えます。
その後、海外に駐在する人材も出始め、数年すると、コンサルティング案件も受注できるようになってきました。
最初に受注したプロジェクトは、小さな案件がほとんどでしたが、自ら発掘し、受注にこぎつけたという成功体験が、メンバーのやる気を増すこととなりました。
そして、5年もすると、海外に出て働くメンバーの数も、10名を越えるチームとなりました。
この経験から、ことを始める最初に、目標と方針をしっかり出しておけば、後は、やる気のあるメンバーを信じ、自ら考え、判断し行動してもらうことで、部下はきちっと仕事を進めてくれることを学びました。
部下の働く意欲を駆り立てる
ここで紹介する話も、「地の業火」からです。
尾張城主の吉通が急死した真相究明のため、聡四郎は、新井白石の命を受け、京を訪れました。
幕府の要職と深いつながりをもち、その関係を利用して莫大な財産を築いてきた、豪商、紀伊国屋文左衛門が、ある意図をもって聡四郎に近づき、京への旅に同行することになりました。
京への途中、草津の宿に聡四郎と文左衛門一行がやってきたときの話です。
何人かの使用人を伴った文左衛門が、草津でも指折りの宿に宿泊することになりました。
当然、使用人は、もっと格下の宿にとめるのであろうと思っていた聡四郎でしたが、文左衛門は、使用人も同じ宿に宿泊されるということで、その理由を文左衛門に問うのでした。
ここで紹介する一節は、文左衛門が使用人をどのように使いこなすかについて、答えた言葉です。
(聡四郎)「定宿だと言ったが、使用人たちもここを使うのか」
ふと聡四郎が気になった。
(文左衛門)「さようで」
「その費用は」
「もちろん、店が支払います」
聡四郎の質問に、みょうなことを訊くと、紀伊国屋文左衛門が首をかしげた。
「いや、使用人にはもっと安いところをと思ったのでな」
すなおに疑問について聡四郎は告げた。
「ああ。そのような店もあると聞きまするが。それは大きなまちがいで。旅は疲れるものでございまする。その疲れを残したまま取引に入っては、考えがまとまらず相手の思うままにされてしまうことになるやもしれませぬ。
わたくしは商人。取引で儲けたかどうかが、お侍さまで言う戦に勝ったかどうかで。十分休養を取って意気のあがる兵こそ、戦場で活躍する。
使い捨てるつもりで雇った者は、主のために必死になってくれませぬ。」
紀伊国屋文左衛門が、聡四郎を諭すように語った。
「なるほどな、それが人を使うこつか」
利を上げるためにどのように人をつかったらよいか、常に商売の戦場にいる文左衛門との意識の違いが明確な紀伊国屋の言葉でした。
気分よく仕事に従事する部下
これも海外事業を進めていたときの経験です。前述の紀伊国屋文左衛門が、使用人をいかに使うかについて語っていたことに通じる経験でもあります。
海外事業を進めている中で、重要な取り組みの一つと考えたことが、いかに海外での滞在期間中の仕事を効率的に行うかということでした。
相手国の関係者とのアポイントメントを取り、効率よく打ち合わせの時間をとってもらい、案件形成についての先方の了解を得るかが、滞在中の重要な業務でした。
このため、現地について、直ちに、先方との打ち合わせに入ることが望まれました。
そして、その打ち合わせでは、相手の話を聞き、十分にこちらの考えを伝えることができるよう、すっきりした頭で仕事をする必要がありました。
そこで、問題になった点が、飛行機で移動するときにエコノミークラスで行くか、ビジネスクラスで行くかという点です。
現地についたならば、すぐに行動し、先方としっかりした打ち合わせができるような状態にすることが必要でした。
このため、移動時間に十分体を休めておくことが効率的と考え、移動には費用の面での負担は増えますが、仕事の効率を考え、ビジネスを使うことにしました。
メンバーからも「それだけ自分が期待されているのだから、現地での仕事をしっかり成果の上がるものにしなければという考えになった」という話も聞こえて来ました。
経費の負担は増えましたが、部下にいかにやる気を起こして仕事をしてもらうかといった点からは、妥当な判断であったと考えた経験でした。
まとめ
組織として、ある大きな目標に向けて動き始めたときに大切なポイントは、共に働くメンバーが、いかにやる気をもって行動するかだと思います。
そのためには、「部下を信用する」ことと「働く意欲を駆り立てる」ことが、大切であることを、上田氏の作品と私の経験から紹介しました。