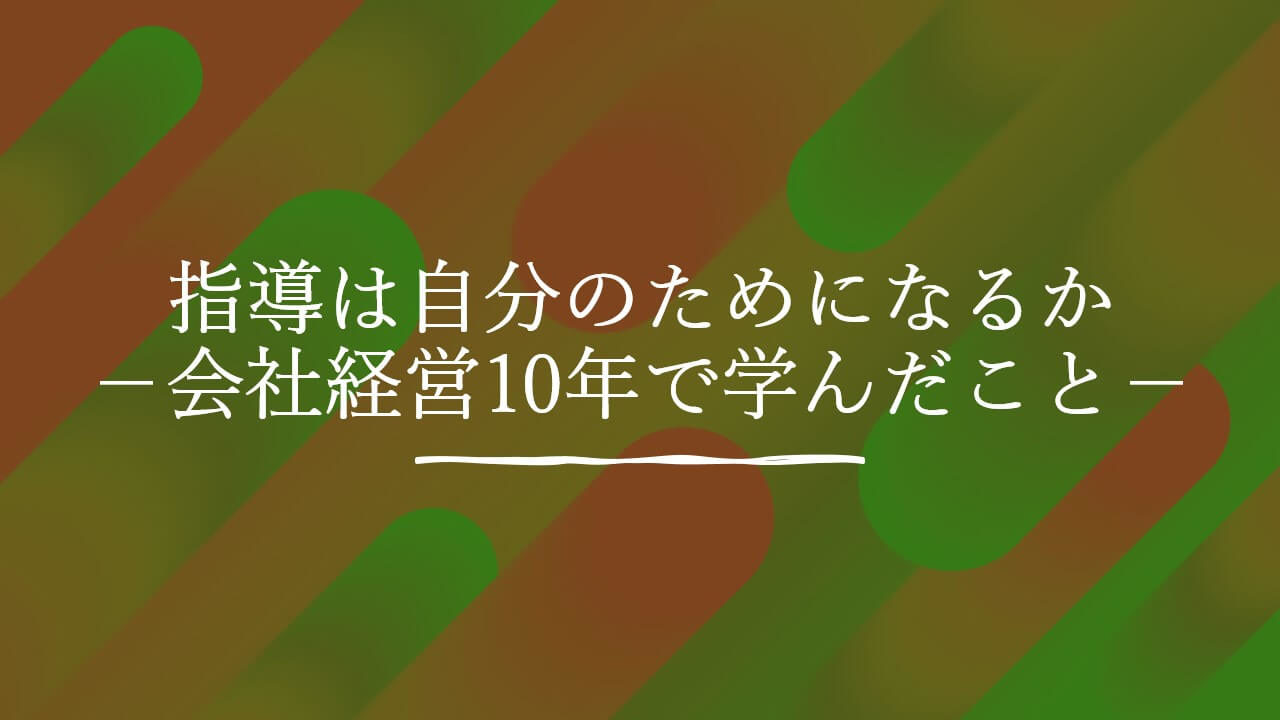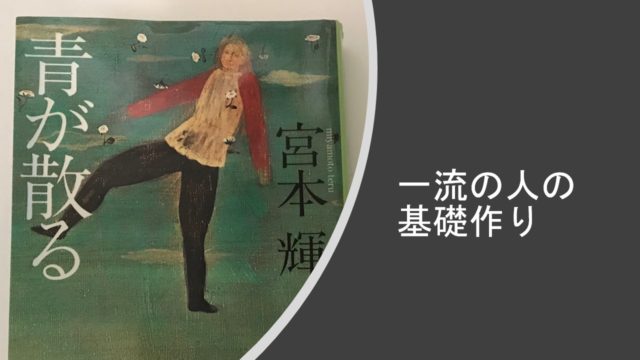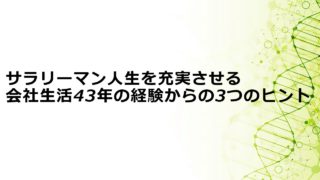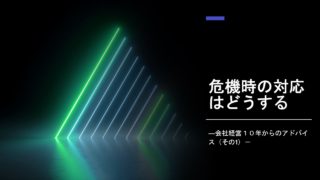会社生活を続けていると、いつか部下を指導する立場になります。
自分の仕事が忙しい中で部下を指導する、さらには成長の後押しをするとなると、面倒で力が入らないことがあるかもしれません。
しかし、昔からよく言われるとおり、「部下を指導することで学ぶこと」は多いと思います。
私も、40代半ばに課長となり、60代で社長を経験するまで、多くの部下とお付き合いする機会がありました。
課長になったときには、1対1で指導することが多くなりましたが、社長となると全社員の成長戦略を立てる必要があり、部下を指導するということが経営上の課題でもありました。
このような経験から、指導することで学べることは多くあるというのが実感です。
ただし、指導するやり方が、部下の成長にも自分の学びにも大きく影響することを学んできました。
作家、今野敏氏も空手の技を磨く主人公を題材とした小説の中に、弟子の指導のあり方について触れる一節があります。
今回は、今野敏氏の小説からの引用と、私の経験からの教訓として、2点を紹介します。
① 指導で学べること
② 指導で気を付けること
指導して自ら学べること2点
部下もしくは弟子を指導していて学べることは幾つかあると思います。その中で、私の経験から学んだ大きなものとして、
① “自分が分かっていなかったことに気づく”
② “自らを鍛え直すきっかけとなる”
があげられます。
自分が分かっていなかったことに気づく
ダムの建設所に勤務していたときの経験です。30代後半で管理職となり、部下も数名いました。
ダムに付帯する構造物の設計をある部下に任せることで、技術力を向上してもらうことにしました。
自分自身は、同じような構造物を設計してきた経験があることから、どのような構造物になるかはだいたい見通せていたつもりでいました。
その部下が、構造物の設計で重要な条件である、地震とか水圧に対する荷重をいかに設定するかで悩んでいました。
その話を部下から聞き、すぐに解決に向けた指導ができると思っていたものの、荷重の組み合わせなどについて、前に経験した構造物とは違った設計をする必要があることがわかりました。
改めて、過去の同種の構造物の設計事例をひも解くなどし、部下とともに、その問題の解決に励みました。
部下を指導することをきっかけに、課長になったからといって、技術力がそれで向上することはないということを改めて認識するとともに、さらなる研鑽の必要性を学んだ経験でした。
自らを鍛え直す-人に教えることも稽古-
ここでは、今野敏氏の小説「武士マチムラ」から、“自ら鍛え直す”の実践の例を紹介します。
小説「武士 マチムラ」の舞台は江戸時代後期、薩摩藩の支配下にあった沖縄です。
主人公の沖縄の武士、松茂良興作は、子供のころから空手の武術・手(ティー)に強い関心を持ち、父親からの手ほどきを経て、厳しい鍛錬を長年にわたり継続します。
一度手の型を見ただけですぐに覚えてしまう異質な能力を持つ松茂良は、沖縄でも名を馳せる武士(ブサー)となりました。
小説では、松茂良が門外不出の武術・手を厳しい訓練の中で習得していく姿を描いています。
また、一人の武士として、薩摩藩の横暴な行為に対し奮闘する松茂良の姿と、その当時の沖縄に対する思いを描いています。
そのような中、松茂良が武士として認められ、沖縄でも名を馳せるようになり、弟子になることを望む者が出てきました。
ここで紹介する一節では、はじめてで弟子を迎え、鍛錬を始めたときの松茂良の心の中を描いています。
(比嘉盛栄:初めての弟子、幼馴染)「実は頼みがある」
興作は、比嘉盛栄に尋ねた。
「頼みというのは、何だ?」
「有名な武士松茂良に、手を教わりたい」
一瞬、皮肉だろうかと思った。
———-
いわば幼馴染に、武士とよばれて、素直に受け取れなかった。
だが、どうやら皮肉ではないらしい。盛栄の表情は真剣だった。
———-
日が暮れると、興作は盛栄の家の裏にある広場に行った。そこで盛栄が待っていた。
興作はまず、自分がやったように駆け足と石の持ち上げをやらせることにした。
盛栄は最初、そのきつさに驚いた様子だった。石を抱いて持ち上げる稽古を終えると、もう何もできないくらいに疲れていた。
気の毒に思ったが、ここで手を抜いては立派な武士にはなれない。興作は怨まれるのを覚悟の上で厳しく指導した。盛栄も負けん気を発揮して頑張った。おかげですぐにナイファンチを学ぶまでになった。
人に教えるようになると、自分の型もおろそかにはできなくなる。正しい型ができないと、人に正しい型を伝えることはできない。
だから興作はますます丁寧に型を稽古するようになった。人に教えることも稽古なのだということを、初めて知った。
(今野敏著 武士マチムラ)
適切な指導をするために留意すること2点
部下の成長を後押しすることができ、しかも自分の成長にも役立つ“指導”のあり方について、気を付けなければならない重要な点はどのようなことでしょうか。
この点についても、私の経験から2点を挙げることができます。
① 自分が指導していることはわかっているはずという思い込みをもたないこと
② 相手が納得するまで対話を繰り返す忍耐力を持つこと
思い込みをもたず、忍耐力を持って指導する
あるコンサルタント会社の社長に就任した時の経験です。
会社の社長となり、将来の会社の成長を確実にするため、これまでの経営を変革する必要がありました。その中で、大きな改革が必要となったことに、社員の意識改革がありました。
それまでの会社では、上からの指示を待って行動するという受動的な仕事の進め方をする社員が大勢でした。また、部門間の連携がなく、まさに縦割り的な仕事の進め方をしていました。
このような状況があったことから、経営改革を進めるうえでは、社員の意識改革を目指すことは必然な成り行きでした。
社員の意識改革を自ら先頭に立って進めていくことにしました。まさに、社員全員を相手に、意識を変えることを目的とした指導を実践することにしました。
当初は、受動的な仕事とか、縦割り的な仕事でのやり方ではどのような問題が生じるか、どのようにすべきか、私から一方的に、いろいろなテーマを取り上げて社員に発信していました。
何度も話をしているのだから、こちらから伝えたいと思っていることは伝わっているはず、といった思いが常にありました。
しかし、半年ほどたっても、社員の理解が得られていないことが、社員へのアンケート調査で分かってきました。
幾つか原因がありましたが、その中で大きな原因が、一方的に話をしているだけでは、社員の納得感は得られないということでした。
こちらが真剣に話をしていれば理解してもらえるはず、といった思い込みが、社員の心に響かない大きな原因であると反省しました。
一方的に話をするだけでは、意識改革は進まないことがわかり、じっくりと、腰を据えて意識改革に取り組むことにしました。
実践したことは、社員一人ひとりが納得するまで、対話することでした。全社員を集めてのワールドカフェ、部門単位の懇談会、さらには、年齢別の懇談会を継続して実行しました。
こちらの意図していることを話し、何に社員が疑問を持っているかをよく理解しすることに努めました。
また、社員からの疑問に対しては、丁寧に説明し、納得してもらうことに時間をかけました。
経営改革をスタートさせて2年経つと、意識の変化がみられるようになり、社員の多くが、これまでの仕事のやり方を見直すようになり、それに合わせ、事業の方も順調に成長することができました。
まとめ
部下を指導することで、自分自身が学ぶことは多くあります。
今野敏氏の小説と私の経験から、事例を紹介しました。時間がないとか、自分には関係ないからといって部下を指導しないことはやめ、積極的に部下の指導あたることが、自分の成長にとって必要なことと思っています。
また、私の経営改革の事例は、部下を指導するときにも同じことがいえる事例だと思います。
自分が頑張っているのだから、部下はわかってくれているはず、といった思い込みは労力を要するだけで、部下の育成には、一切役立ちません。
何をすべきか話をし、対話を繰り返す中で、自分で考える時間を与えることで納得感が生まれ、成長していくものだと思います。