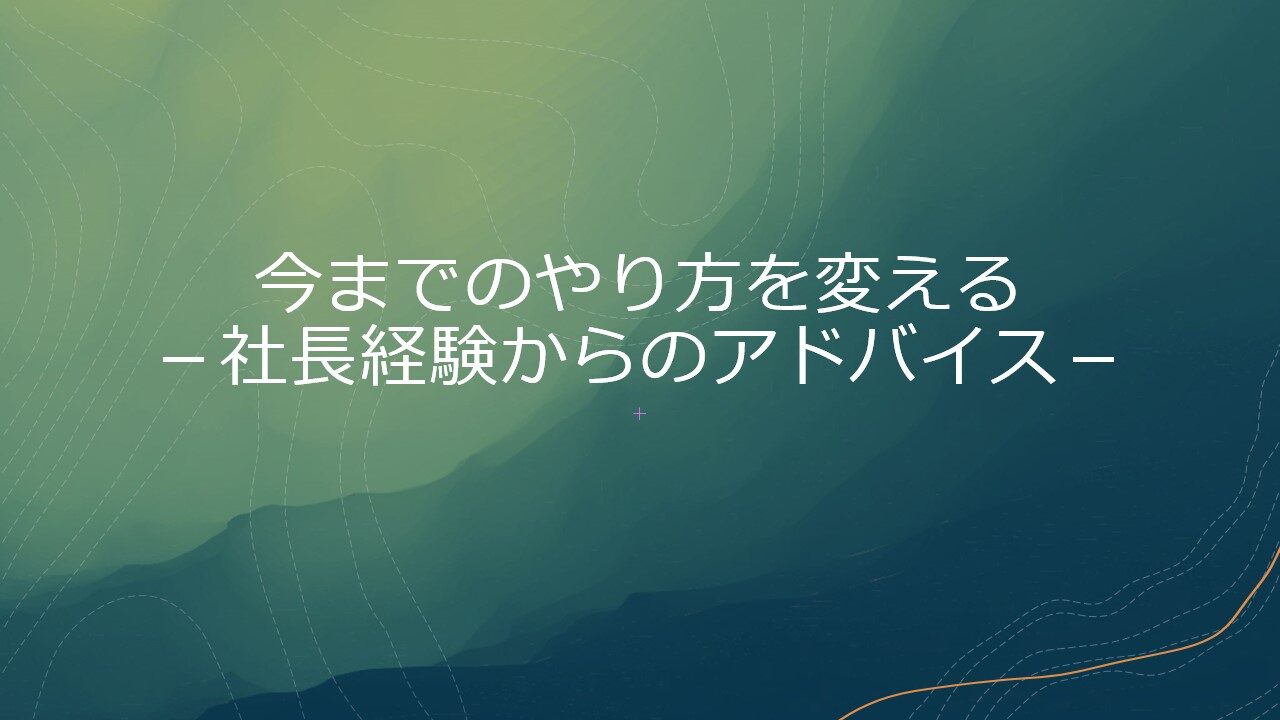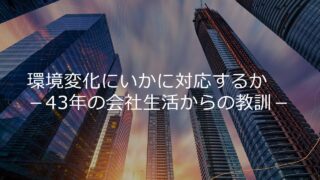前回のブログでは、「環境変化にいかに対応するか」と題して発信しました。
前回の内容と似たところがありますが、今回は、今までのやり方を踏襲してしまうことによる弊害とその対策について紹介します。
環境が変化し、自ら変わっていかなければならない中、今までのやり方を捨てることができずに環境の変化についていけず、対応が後手になることがあります。まさに、仕事の断捨離ができず、現状に対応できない状況かと思います。
司馬遼太郎は、その作品「坂の上の雲」の中で、旧大国スペインと新興国アメリカの海軍の考え方を例にとり、固定観念にとらわれることの弊害を紹介しています。
私も、会社経営に携わるようになり、これまでのやり方を捨てきれずに、会社の変革に支障が生じる懸念が生じ、このため、いろいろな対策を講じた経験があります。
今回は、司馬氏の作品と私の経験から、固定観念や今までのやり方を捨てることができないことによる弊害と、その脱却方法について紹介します。
固定観念を捨てるには素人のほうが良いのでは
日清戦争が終わり、秋山真之は海軍大尉としてアメリカに留学し、しばらくすると、スペインとアメリカがキュウーバの独立をめぐり戦争が勃発しました。
真之は、その海戦に観戦武官として参加することになり、旧泰然とするスペイン海軍に対し、新興国のアメリカ海軍が勝利する場面を逐一見ることができました。
その海戦を視察し、真之は、スペインがなぜ負けたのか、旧弊にしがみつくスペイン海軍を反面教師に、日本海軍の改革の必要性を学ぶのでした。
真之は、アメリカ滞在を終え、英国を回って日本に帰国し、子供のころから仲の良い子規のもとへ病気見舞いに訪れた。
訪れたのは、子規が、余命が少ないことを知る中、短歌の世界の旧弊を打ち破ろうとしていたときでした。
ここで紹介する一節は、子規から、その熱意を聞き、真之が現状の日本海軍の将来のありようについて熱く語る場面です。
真之は、滞米中からおもいつづけていたことを、子規に話した。
「どうせ、あしの思うことは海軍のことじゃが、それとおもいあわせながらいま升(のぼ)さんの書きものをよんでいて、きもにこたえるものがあった。升さんは、俳句と短歌というものの既成概念をひっくりかえそうとしている。あしも、それを考えている」
「海軍をひっくり」
「いや、概念をじゃな。たとえば軍艦というものはいちど遠洋航海に出て帰ってくると、船底にかきがらがいっぱいくっついて船あしがうんとおちる。人間もおなじで、経験は必要じゃが、経験によってふえる知恵とおなじ分量だけのかきがらが頭につく。知恵だけ採ってかきがらをすてるということは人間にとって大切なことじゃが、老人になればなるほどこれができぬ」
(なにをいいだすのか)
と、子規は見当がつかぬままに、うれしそうに聴いている。
「人間だけではない。国も古びる、海軍も古びる。かきがらだけになる。日本の海軍は列強の海軍にくらべると、お話にならぬほどに若いが、それでも建設されて三十年であり、その間に近代戦を一度経験し、その大経験のおかげで知恵もついたが、しかしかきがらもついた」
「そげなものか」
———-
「かきがらは人事だけではない。あしは作戦屋で軍政には興味をもたぬけん、人事のことは言わぬ。あいの言いたいのは、作戦じゃ。作戦のもとになる海軍の頭じゃ」
「古いのか」
「古今集ほど古くなくても、すぐふるくなる。もう海軍とはこう、艦隊とはこう、作戦とはこうという固定観念(かきがら)がついている。おそろしいのは固定観念そのものではなく、固定観念がついているということも知らず平気で指令室や艦長室のやわらかいイスにどっかりとすわりこんでいることじゃ」
真之は、アメリカ海軍の話をした。
「アメリカ海軍は、素人じゃと思うた」
と、言った。
「日本の方が玄人か」
「世界一の玄人であるイギリス海軍に学んだため、当然ながら玄人じゃ。あしの玄人の目でアメリカ海軍をみると、やることなすことがじつに素人くさい。しかし、おそろしさはその素人ということじゃ」
素人というのは知恵が浅いかわりに、固定観念がないから、必要で合理的だとおもうことはどしどし採用して実行する。ある意味ではスペイン海軍のほうが玄人であったが、その玄人が、カリブ海で素人のために沈められてしまった、と真之はいう。
(司馬遼太郎著 坂の上の雲第二巻)
固定観念のために、柔軟性をうしなうことの弊害を述べるとともに、むしろ素人の柔軟性で合理的な方策をとることができることを、真之は強く語っています。
経営改革で出会った抵抗
私が土木建築関係のコンサルタント会社の社長となり、将来の成長を目指して経営改革をスタートさせたときの経験です。
その会社は30年以上続いた会社で、ある会社の子会社ということもあり、その親会社から多くの仕事を受注することができることから、親会社以外に広く市場に出ていく必要がありませんでした。
このような環境下で仕事を進めていたことから、経営改革を進めるうえで、会社の制度や仕事のやり方などで、支障となることが少なからずありました。
営業という仕事をとっても、親会社以外の市場に出ることがほとんどなく、待っていれば仕事が来るということで、どうしても受動的な営業になってしまっていました。
また、組織の壁が高く、部門が共同して仕事をするということにも慣れていませんでした。
これらの具体的な事例以外で問題であったのは、そのような旧態然とした仕事のやり方では現状を変えるための改革ができない、ということを理解する社員がほとんどいないことでした。
このため、経営改革を始めてすぐに取り掛かったのが、これまでの仕事のやり方、制度を変えること、また、社員に変っていく必要があるという意識を持たせることでした。
そこで、これまでのやり方を変え、社員の意識を変えるためにとった方策が以下の4点です。
- 会社として改革で目指す理想の姿と目標を明確にする
- その理想の姿を社員一人ひとりが理解する
- 一人ひとりが、その目標に向け、何を実施するのか立ち位置を明確にする
- 社員一人ひとりが自ら考え、判断し行動する
これら方策をどのように展開したか、概要を紹介します。
各方策の実施事例
(1)将来の理想の姿と目標を明確にする
経営改革を進めることで目指す理想の姿を明確にし、10年後の会社がどのような経営状態になるか、売上高、利益などの目標を明確にしました。
そして、そのような理想の世界では、社員一人ひとりが、がわくわく感をもって働くことができるようになることを社員に提示しました。
(2)社員の理解を得る
経営層からただ、将来の姿を発信しても、なかなかに社員の理解を得ることはできませんでした。
このため、社長自ら社員との対話集会を開き、説明とともに、社員からの質問を受け理解活動を進めました。
さらに、社員全員が集まって、将来の会社の姿をどうするかについての集まりも開催しました。
最初の頃は、従来の仕事のやり方に固執する人から、将来の姿への不安などに関する質問が出ましたが、このような活動を繰り返す中で、また、業績が向上する中で、社員の意識は大きく変化していきました。
(3)社員の立ち位置を明確にする
会社が変わっていく必要性の理解は進んだものの、将来の会社では、本当にわくわく感をもって仕事ができるのかという疑問が、社員の満足度調査からでてきました。
このため、会社が成長する中で、社員一人ひとりがその成長のなかで何を担うのかをはっきりするようにしました。自分が会社に対してどのように貢献しているのかがはっきりするようにした訳です。
具体的には、会社の目標を紐解き、各自の目標を定めるようにし、その目標に対する成果については、年度末に評価し、その結果に応じて、報酬が決まるシステムとしました。
(4)自ら考え判断し、行動する
各自が会社目標と連動した目標をさだめるとともに、社員のモチベーションを上げるためにとった方策が能動的な仕事のやり方を取り入れたことでした。
仕事を進めているときに生じる課題について、自ら考え、判断し、行動するように仕事のやり方を変えました。
まとめ
会社そのものそしてその中で働く社員も、長年続けてきた仕事のやり方については、特に、経営が危なくなるなどの危機に遭遇する事態にならないと、今までのやり方を打破することが難しいと思います。
しかし、会社の周りの経営環境は常に変化し続けており、その変化に対応していかなければ、近い将来、行き詰ってしまうことは、このコロナ禍の世界で一層はっきりしてきています。
常に変わっていく姿勢が必要であり、そのために、私が経験した、4つの方策が参考になればと思っています。