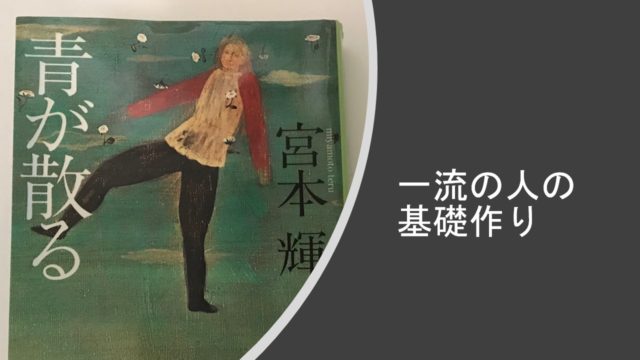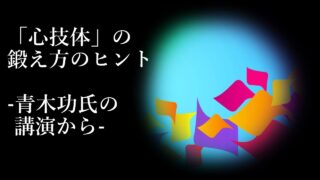生き生き働き、仕事で充実感を得るためにはどうすればよいのでしょうか。
これまでも、“いきいき仕事をするにはどうしたらよいか”について、このブログで紹介してきました。
前にもいくらか触れましたが、今回は、仕事で充実感を得るための方法として“自ら考え行動する”ことについて、今少し詳しく紹介します。
今野敏氏は、その作品の中で、この点について触れています。
ある犯罪事件の捜査の過程で、ベテラン刑事が若手の刑事に対し、なぜ自ら考え、行動して捜査にあたらなければならないか、諭している場面です。
私も、建設現場で、ある仕事を任せられ、自ら考え、判断していたときに仕事の面白さを感じていました。
また、後年、ある会社の社長になったときには、社員に充実感を得てもらうためにどうすべきかいろいろ試行を繰り返し、結局、社員一人ひとりが、自ら考え、判断し行動することがいちばんの方策であることを学びました。
今回は、今野敏氏の作品と私の経験から「仕事で充実感を得るために方のとして、自ら考え、行動する」について紹介します。
警察の捜査は自ら考え、行動することが重要
小説「カットバック」は、東京警視庁大森警察署管内で起きた、撮影現場での殺人事件を取り上げています。
主人公である楠木は、映画撮影のロケ現場での支援を手掛ける警視庁内に設けられた部署、フィルムコミッション(FC室) の一員です。映画撮影への協力要請があり、久しぶりに撮影現場に出動しました。
出動したその日の朝、殺人事件をストーリーとした映画の撮影現場で、わき役を務める俳優が殺されました。
楠木は、捜査に関わりのないメンバーでしたが、犯罪の端緒に立ち会ったことから、所轄の大森警察署のベテラン刑事である戸高と行動を共にすることになりました。
状況証拠から、犯人はこの撮影に関係した者に限られることがわかりましたが、なかなかに犯人の絞り込みができない状況でした。
そのような中、戸高と若手刑事の矢口がコンビを組んで、現場の捜査にあたります。
教科書的な捜査しかとろうとしない矢口刑事に対し、戸高刑事は、コンビを組んだ時から不満を感じています。
ここで紹介する一節は、そんな矢口の捜査姿勢に、戸高刑事がついに堪忍袋の緒が切れ、犯罪捜査のあり方を説く場面です。
楠木たちは、メーク室や衣装部となっている会議室を出た。
矢口が言った。
「結局、何も聞き出せなかったじゃないですか。もっと粘れたと思いますよ」
戸高は面倒くさそうな顔をしただけで、何も言わなかった。
楠木は尋ねた。
「これからどうします? 地域課のパトカー、行っちゃったし——」
戸高は、質問にこたえずに、何事か考えている。
楠木はどうしていいかわからず、ただ戸高といっしょに歩いていた。戸高は、撮影の現場に向かっているようだ。
矢口が言った。
「捜査本部に戻りましょう。自分らは、桐原美里(俳優)から話を聞けと言われただけですから」
戸高が言った。
「俺は学校の成績がよくなかったんだ」
矢口が怪訝そうな顔になった。
「は——?」
楠木も、戸高が何を言っているのかわからなかった。
戸高の言葉が続いた。
「先生の言うことを聞かなかったからな。あんたは違うだろう。きっと先生の言うことをよく聞いた優等生だったんだろう。
矢口が言った。
「まあ、勉強はできたほうですね」
「学校の成績ってのは、先生の言うとおりにしていれば上がるんだ。だけど、警察の捜査はそうはいかない。自分で考えて、自分が動かなきゃだめなんだよ」
「捜査において、独断専行は一番いけないことだと教わりました」
「自分で考えることと、独断専行は別なんだよ。まったく、最近の若い刑事はおりこうさんばかりで役に立たない」
矢口はむっとした表情で言った。
「所轄のヒラ刑事に、そんなことをいわれたくありませんね」
「所轄も本部も関係ないよ。要は使えるか使えないかだ」
「使えるって、どういうことです?」
「だからさ、自分で考え頭があるかどうかなんだよ」
(今野敏著 カットバック)
経営改革を目指したときの社員の意識
私が土木建築関係のコンサルティング会社の社長を務めていたときの経験です。
会社の持続的な成長を求めて、就任早々に事業のあり方、組織、そして仕事のやり方を大きく見直す必要がありました。
それまで30年以上にわたり、大企業の子会社ということで、仕事の多くは親会社からの受注が占めていました。
しかし、私が社長に就任したころから、親会社からの受注が減り、今までのやり方では、成長はおろか、現状の収支状況を持続することも難しい状況でした。
会社の成長が止まり、事業が縮小していく中で、社員の給与もカットされている状況で、社員の中には、将来の生活を不安視する人も増えつつありました。
このため、経営改革にあたって、まず実施しなければならないことが、社員の処遇を元に戻し、社員の会社に対する不安を取り除くことでした。
処遇の見直しについては、同時に進めていた、事業のやり方を変える方策が功を奏し、業績が上がって来たことから、翌年には、その見通しが尽きました。
処遇改善が済み、社員のやる気も持ち直してきたことが見えてきたことから、社員の会社に対する意識調査を実施しました。
その結果、私にとって関心の強い社員の意識として2つのことが見えてきました。
一つは、会社に対する満足度が、同規模の会社の社員の満足度とほぼ変わらない状況まで改善されたことです。
いま一つは、給与など処遇面では満足したものの、仕事のやりがいについては評価が低いことでした。
このことから、基本的な会社への満足は満たされているものの、仕事に対してやりがいを持てる仕事のやり方を考え、社員が生き生きと働ける職場づくりをしなければならないことがはっきりしました。
生き生き働くための方策-“自ら考え、判断し、行動する”
経営改革をスタートさせるにあたり、10年後の会社のあるべき姿を明確にしました。その理想の姿に向け、会社としての具体的な目標として、売上高、利益も明確にしました。
事業を進める各実行部隊である技術系本部では、会社の目標から割り当てられた個別目標を目指して、事業を展開するようになっていました。
前述したように、1年ほどで、その方策は効果を見せ始め、業績も向上してきました。
しかし、社員の仕事に対する満足度は、それほどには上がってきていませんでした。なぜ、そのようなことが起こっているか検討を進めました。
社員との懇談会、アンケート調査などを実施しました。
その結果わかったことはが2点ありました。
(1)これまで上司から仕事を与えられており、上司の指示に従った仕事をやっていれば よいという、受動的な姿勢であること。このために、仕事をやらせられているという意識が強く、仕事を進んでやっているという意識が低くなっていました。
(2)本部ごとに会社の目標達成のための目標は定められていたものの、社員一人ひとりの目標については、会社の目標に対する位置づけが不明確であったこと。このために、社員が、自分の会社での立ち位置が不明確であり、甲斐さに対し、また、社会に対しどのように貢献しているかがつかめなかったことがあります。
このような検討を踏まえ、社員が生き生きと働くための基本的な方策として、“自ら考え、判断し、行動する”ことを実践することにしました。
社員一人ひとりに、会社の目標に連携するように目標をたて、その目標に向かい、どのように仕事を進めていくかは、自分で考えることが大きな柱でした。そして、仕事を進める中で課題が生じれば、自らの判断で方策を考え、実行することにしました。
もちろん、これらのプロセスの中で、上司のアドバイス、指導は当然なされるような仕組みとしました。
この方策がスタートするまでに4年ほど費やしましたが、その後のアンケート調査では、社員の仕事へのやりがいは、格段に上がってきました。
まとめ
仕事をしていて、その仕事にやりがいを見出せれば、それほど充実した生活はないと思います。
では、どうすれば、そのような充実した仕事ができるようになるのでしょうか。
私の経験からは、仕事に対する姿勢が大事で、受動的ではなく、能動的に行動していくことが必要であると思います。
そして、そのためにも“自ら感が、判断し、行動する”姿勢が必要なのではと思っています。