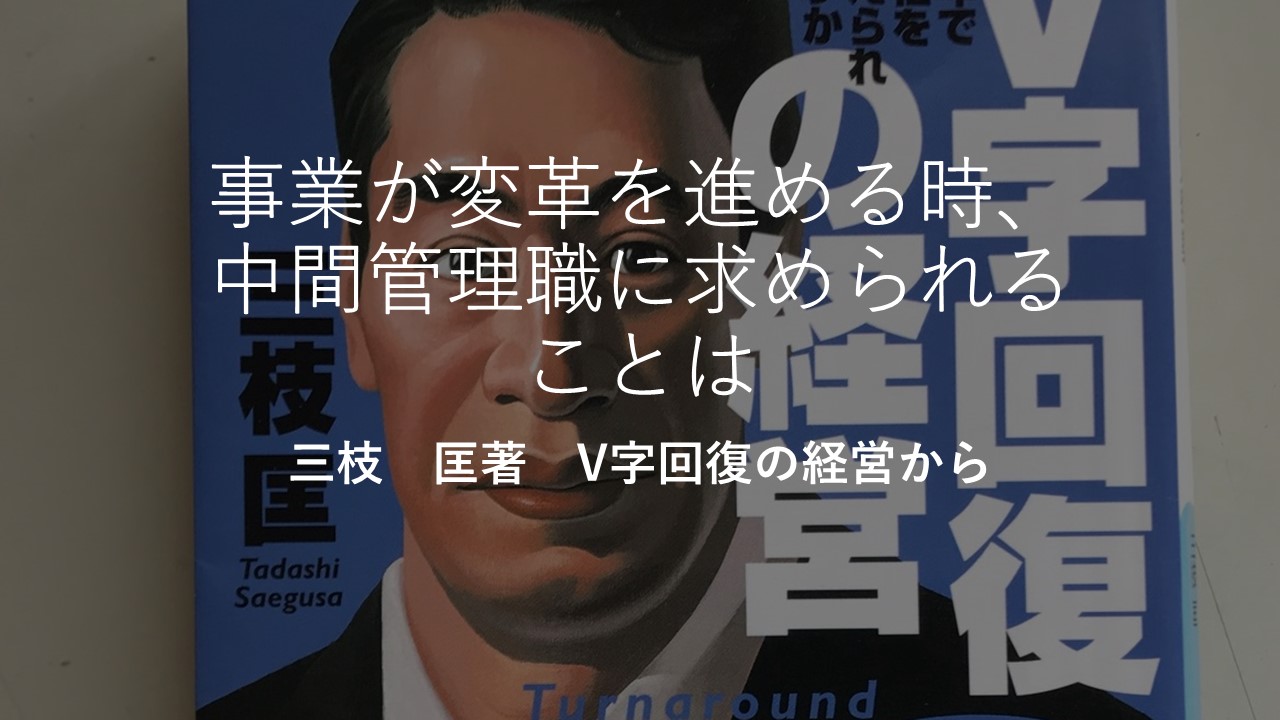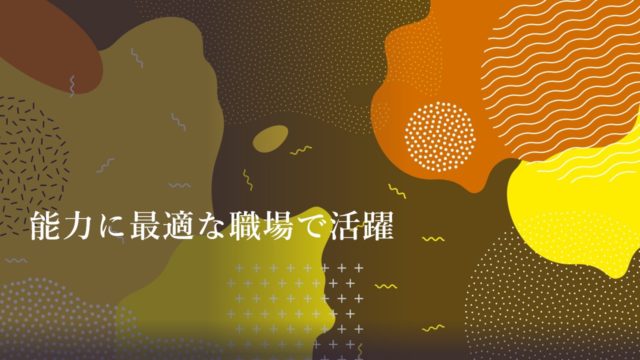会社で変革を敢行するとき、課長、グループマネージャーといわれる中間管理職が、重要な役割を果たします。
また、その立ち位置は、上には部長ほか上司がおり、下には部下がおり、円滑に組織を動かす要(かなめ)的な存在でもあります。
企業の再建支援で実績のある三枝匡氏は、その著書で中間管理職が事業再生でどうあるべきかを説いています。
また、私の会社経営での経験から、お客様対応、商品開発を担う中間管理職は、20年ほど前にテレビ放映された戦争ドラマ「コンバット」のサンダース軍曹の行動がヒントになるのではと思っています。
改革に背を向ける中間管理職の姿勢
三枝氏の著書「V字回復の経営」の中で、ある不振事業の再建に取り組む主人公が、その改革の重要なプレゼンの場で傍観者的な行動、発言をする中間管理職に対し、その甘えとしか言えない態度に怒りを覚え、次のように語るのでした。
そこには自己責任を認識できず、すべてを人のせいにして当たり前という、日本企業に広くみられる社員の幼児性がある。
しかもそうした甘えた管理職は、「顧客」や「競争」の現場からもっとも遠い本社管理部門に多く見られる。おまけに、その管理部門が「代理症候群」に助けられて、社内で一番威張っていたりするのだから、これほど始末の悪いことはない。
「頼むから、分かってくれよ—」
それが怒りをのみ込んだ後の、黒岩莞太の切なる心情だった。
出典:三枝 匡著 V字回復の経営
中間管理職が、自ら考え、判断し行動する
私が経営参画した会社では、事業拡大のため、これまでの顧客以外の市場へも商品を展開することが重要な方策でした。
事業を拡大すれば、当然、お客さまの数が増え、それとともにお客さまのニーズ が多様化します。
このため、現状の営業部門の行動パターンでは、お客さまが離反し、拡大はおぼつかなくなることが懸念されました。
そこで、私は、グループマネージャーを対象に、繰り返し次のような話をしてきました。
これから我々がお付き合いするお客さまから見れば、わが社は、多数ある同一企業の中の一つであることを意識する必要があります。
お客さまから、いろいろなニーズをお聞きしたときに、迅速かつ能動的に対応するのでなければ、お客さまの信頼を失い、そのお客さまはすぐに競合会社に仕事の話をもっていってしまいます。
このため、いかにお客様のニーズを吸い上げ、その要望にスピード感をもって応えるかが重要になります。
そういった意味で、お客様と直接触れ合うグループマネージャーが、自らその状況を把握し、自ら判断して行動に出るスピードが必要です。
こうすることで、お客様の心をとらえ、信頼を勝ち取り、競合に買って、仕事を受注できるようになると考えています。
また、お客さまに届ける商材、技術は、他の競合の先を行くものでなければ なりません。一歩後れを取れば、すぐにその企業は我々のお客さまに近づき、 お客さまを奪っていくと思います。
その際、 昔、テレビで見た戦争ドラマの主役であった、サンダース軍曹の姿を思い出し、合わせて、この軍曹の行動についても話をしました。
「コンバット」サンダース軍曹の中間管理職としての行動が参考に
コンバットというドラマは、1960 年代に日本で放送されていたアメリカのテレビ番組です。
第二次世界大戦下での、アメリカ陸軍歩兵連隊の一つの分隊を率いるサンダース軍曹の活躍を描いたドラマでした。
彼は、8 名程度の部下を連れ前線での戦いに明け暮れていました。
彼の部隊には二つの敵がいました。
一つは目の前の敵。
また、もう一つがその先の敵です。
前線での戦いの中、いちいち司令部にどうしたら良いかなど問うている暇はなく、軍曹がその場、その場の判断で戦いを進めていかなければなりません。
さらに、その先にいる敵の状況にも目を配り、戦い方を考え、判断し、行動する必要がありました。
この軍曹の行動は、お客さまが増え、多様化する中での、今後の当社のグループマネージャーが取るべき行動に類似するものがあると思っています。
まとめ
事業を立て直す、新たに事業を拡大しようとするとき、中間管理職に求められるのは、顧客、競合を意識した、自らが積極的に参画し、判断し、行動する姿であると思っています。