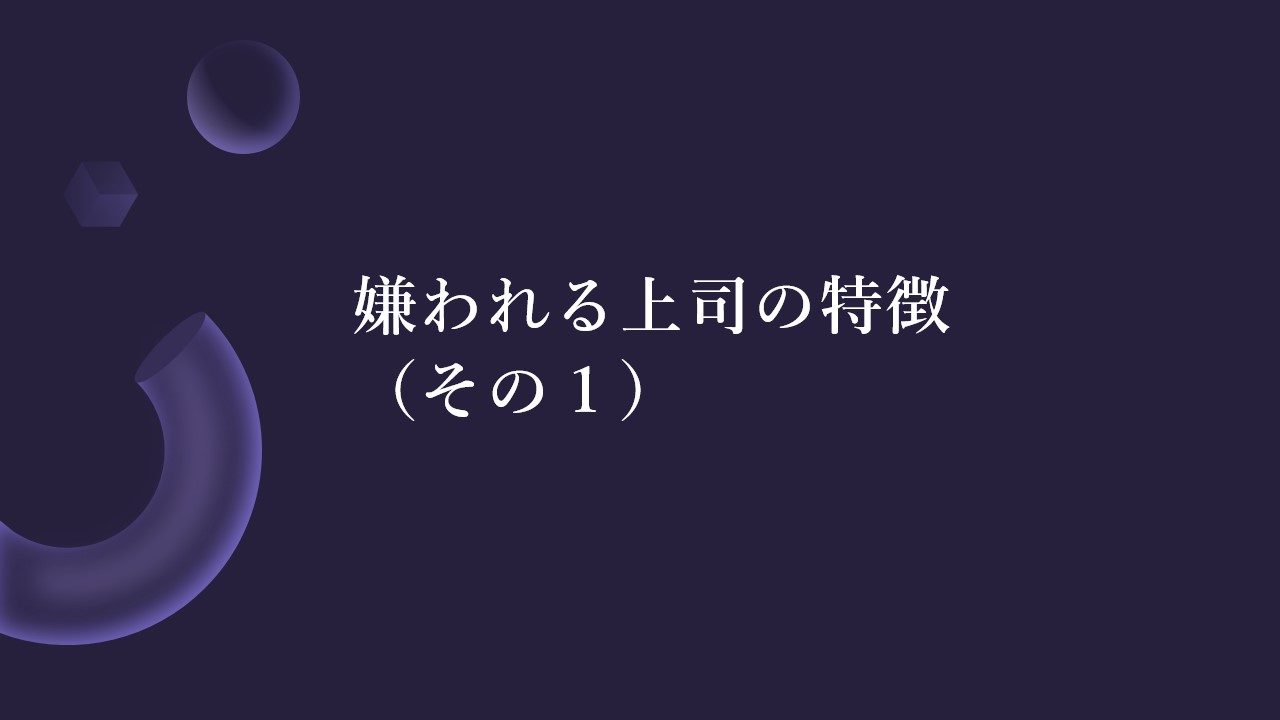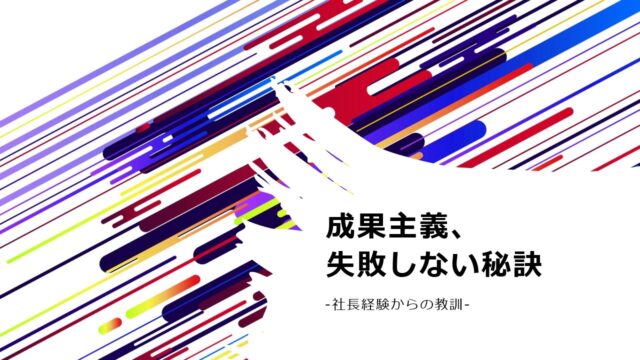サラリーマンとして仕事を続けている中で、「尊敬できる上司」に出会えば、自らも成長し、仕事自体にもやりがいを持つようになります。
一方で、「どうしてもあの上司は嫌い」と、言われる上司もいます。
サラリーマンが嫌う上司の特徴については、「いつも自分が正しい」とか、「攻撃的」とかといった点が挙げられます。
私の経験では、上司に相談をもちかけているのに、アドバイスというより、一方的な発言を返されたり予期せぬ言葉を聞いたりし、上司の上から目線の態度にムッとすることがありました。
さらに、上司が一方的な方向からしか情報を取ろうとせず、判断を間違えてしまうことが上から目線の弊害として挙げられると思います。
宮城谷氏はその著書で、能力の高い人でも、上から目線では判断を間違えてしまう事例を紹介しています。
今回は、宮城谷氏の作品と私の経験から「上から目線の上司の特徴と問題点」について紹介します。
上から人を見ることでは、その人の本質を捉まえられず
宮城谷氏著の「草原の風」の舞台は、紀元前6年から57年の中国で、主人公は、漢の高祖、劉邦の後裔であり、後漢を起こした劉秀です。
まだ十代の劉秀は、叔父の家にあずけられ、その地で農作にいそしんでいました。
他の農人と異なり、劉秀は農作業での手抜きをせず、工作に工夫をし、みのりを豊かにする努力をひたむきに進めていました。また、その工夫を他の人にも進んで教えるなど、人望の厚い人でした。
そんな、劉秀は学問にも優れ、養い親である叔父の勧めなどもあり、時の都、常安(長安)に留学することになりました。
周りの人々は、そこでも劉秀の常日頃の言動に感心し、徳の高さを認めるのでした。
その劉秀が、学費稼ぎのため運送屋をはじめました。ある将軍からの書簡を預かり、人相見の第一人者といわれた許氏のもとをたずねました。
許子の弟子が、劉秀との会話の中で劉秀の優秀さを認め、そのことを許氏本人に語りましたが、人相見の許氏は、目の前にいる劉邦の将来の姿を予見することができませんでした。
(許氏の弟子)「あの若者はなかなかの面相をしていると観ました。英雄の相とは、あれではありますまいか」
許氏は顔をゆがめた。「都内の運送屋が英雄になれようか。なんじは何を観ている。修行が足りぬ。よいか、ここだけの話だが、やがて天に昇る臥龍は、南陽軍にいる(劉秀の留学前居住地)。都内にはおらぬ」
そういう許氏は何を観ていたのであろうか。もっとも劉秀はひたいをかくす幘(頭巾)をつけてうつむきがちであった。人は上から他人を観ては、見そこなうということであろう
出典:宮城谷 昌光著 草原の風
上から目線の上司が引き起こす問題
私は、複数の会社で勤務してきましたが、その中で、上から目線の上司と一緒に仕事をする機会が多くありました。そのときの経験です。
会社では、人事異動はつきもので、そのときにだれが昇進するかは、関係者のもっとも関心のあるところです。
「えっ、なんであの人があのポストにつけるんだよ。上ばっかり見ていて、自分で動こうともしないくせに」といった会話がなされることも多々あるかと思います。
誰が人事を決めるかについては、その組織のトップのかかわりが影響します。そして、人事に影響のあるトップからの言葉だけを聞き、部下の話を聞こうとしない場合に、上から目線での行動を取る上司の多いことを、私は会社生活で見てきました。
ある人が主要な課長のポストに就きました。
その人は、以前から、部下の意見は聞かず、傲慢なところがあり、我々下のものからは、なんであの人が、あのポストに、といった話が出るような人でした。
その課長のもとで仕事が始まりました。すると、自分の上司の言うことについては、ほとんど意義を挟まず、そのまま我々のところにきて「これをやっておけ」といった調子で仕事をする人であることがわかりました。
ある案件を実施するために部長に承認伺いに行ったところ、いくつかの意見が示され、方向性が決まりました。
その方向で案件を進めた場合、関係する部署で大きな問題が生じることが危惧されていましたが、その課長は、部長に反論もせず、ほぼ部長の方針に沿って案件を進めていきました。
案件を進めているうちに、その案件に関係する他部署から重要な反論がなされ、その解決に多くの時間が費やされ、結局、当初案を引き下げることになりました。
もっと、案件に取り掛かる前に、部下や関係部署の意見を聞き、たとえ、権威のある部長であっても、言うべきことは言い、その上での判断で、ことを進めることが必要でした。
この事例は、上ばかりに気をつかい、部下を上から目線で見るだけの上司が陥る事例として多くを学んだ経験でした。
上から目線の姿勢では真の実力は育たず
ここで、話は「草原の風」に戻ります。時は進み、主人公である劉秀が一軍の長となり、頭角を現すようになったときのことです。
劉秀の戦いは、彼の戦略と優秀な将軍の存在で連戦連勝でした。しかし、ある戦いで、劉秀が将来の将軍候補として育てていた若い二人、鄧禹と朱浮に、将来の将軍となるための教育の意味も持たせ、先陣を任せました。
しかし、巧妙な戦略を立てたわけでない敵の攻撃に敗れ、引き下がらずを得ない状況となりました。
なぜ、二人は敗れたのか、若いという理由だけだったのでしょうか。
ここで紹介する一節は、若い時からの人に対する日頃の姿勢の大切さを劉秀が語っている場面です。
連戦連勝の延長上にあるふたりは敵を軽視したのであろう。前方をさぐることなく、兵をすすめた。
李育(敵の将軍)の軍は、そうとうな兵力をもち、しかも潜行していたわけでもないのに、その軍の所在を偵知することができなかったのは、鄧禹と朱浮の将才に限度があるということであった。
その種のことは、若さや未経験を、いいわけにもちこむことができない。生きかたや日常生活のすごしかたにかかわることで、鄧禹と朱浮はひごろ人や物を上から視る習癖をもち、ほんとうの用心深さをもっていないといえるであろう
出典:宮城谷 昌光著 草原の風
能力を磨き上げるためには、若いころからの生き方が大切であり、特に、上から目線で事を済ませることを戒める事例でした。
まとめ
サラリーマンにとって、嫌われる上司と仕事をすることのつらさは、経験した人しかわからないことかもしれません。
そのように嫌われる上司の特徴として、判断に際して、上から目線で物を考えることで、考えに偏りが生じてしまうことがあげられます。
このように、上に立つ者が判断するときに、集められる情報に偏りが生じた場合、周りの状況と整合がつかず、問題を引き起こすことが多々あります。
宮城谷氏の逸話や私の経験から、上に立つ人は、常に立ち位置を部下と同じにし、部下と同じ目線で状況を把握し、その上で事を判断する必要があると思っています。
このような姿勢を上司が持つことで、部下も上司を敬い、やる気をもって仕事につくようになると思います。