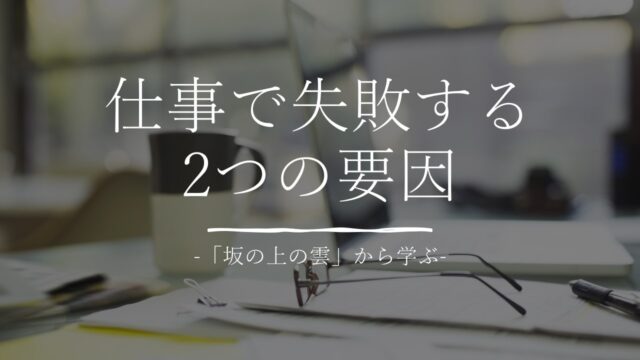会社生活を送っていると、好不調の波が必ずあります。仕事で成果を出したり、あるプロジェクトを成功に結びつけたりと、好調の波が続くと、つい自信過剰となり、驕りが生じてきます。
そして、驕りが生じると、その先の成長への努力を怠ったり、人のアドバイスを素直に聞けなくなったり、いろいろな弊害が出てくるようです。
「驕れるもの久しからず」は、平家物語の冒頭の一節ですが、成功体験から驕った人が、どのような状況に陥り、それが将来的にどのような弊害をもたらすのでしょうか。
作家、柳田邦男氏はその作品の中で、太平洋戦争での日本海軍の事例を挙げ、驕りがもたらす弊害について触れています。
私も、ダムの建設現場にいたときに、自信満々となって取り組んだ結果、後で、トラブルに遭遇しました。そして、調子よく仕事をしていたときに、ある上司から「お前の天狗の鼻をへし折ってやろうか」と、そのときの浮ついた気分を取り払ってもらった経験があります。
今回は、柳田邦男氏の作品と私の建設現場の経験から「成功体験の弊害として、驕りの問題とその対処方法」について紹介します。
驕りの報いは必ずやってくる
小説「零戦燃ゆ」は、零戦の開発から、零戦が最も活躍した太平洋戦争の初期、そして、その弱点を狙われ、その威力を削がれるまでを、日米決戦の全体を通して描きあげた長編小説です。
ここで、紹介する一節は、零戦が、太平洋戦争の初期、世界でも類を見ない高速、旋回能力を携え、米国や英国と戦い、見事な戦果を挙げていたときの話です。
マレー半島の制空権、制海権を狙い進出した日本軍は、他国の戦闘機を凌駕する能力を持つ零戦の活躍もあり、英国が誇る東洋艦隊の艦船を撃破することになります。
この海戦(マレー沖海戦)はまた、大艦巨砲主義を色あせた歴史資料の中に葬り去った事件でもあった。
英東洋艦隊敗北の報告を受けたチャーチル首相は、「生涯で、かくも大きな痛手を受けたことはなかった」ほどの衝撃を受けた。
マレー沖海戦が海軍戦史のターニング・ポイントになるほどの事件であったのなら、日本海軍もまた、この海戦から読み取るべき教訓は多かったはずだった。
だが、巨艦『大和』『武蔵』を最後のよりどころとしようとする大艦巨砲主義は温存されていく。
建艦計画において空母の重要性が認識されるのは、ミッドウェー海戦の敗北以後になる。
(柳田邦男著 零戦燃ゆ 飛翔編)
マレー沖海戦では、イギリス艦隊の主力艦が、日本海軍の戦闘機のもとに撃沈され、大敗した戦いでした。
この事例から、今後は、大規模艦船による戦いより、空母を主体にした航空戦力が海軍の主体となるという重要な教訓が得られるはずでした。
しかし、日本軍は、その勝利の絶頂期にあったためか、その教訓をその後に生かすことができませんでした。
戦争に限らず、一国の経済活動においても、個別の企業活動においても、あるいはスポーツにおいても、ある意味でいちばん難しいのは、自らが勝利の絶頂に立ったときだと、よくいわれる。
勝利に酔い、向かうところ敵なしと驕るうちに、戦訓の陰影に目を向けるのを忘れ、戦う敵あるいは競争相手の状況は変わってゆくのだという鉄則に気づかなくなる。
しかし、その報いはやがてやってくる。”
(柳田邦男著 零戦燃ゆ)
順調との思いから他人のアドバイスを聴こうとしない驕り
私が30代でのときに、ある特殊な構造物を設計する仕事に従事したときの経験です。
その当時、日本ではほとんど用いられていなかった工法を設計に採用することになりました。
プロジェクトチームが設置され、リーダーの下で構造設計を主体に従事することになりました。
日本にも前例がないということで、海外での数少ない事例とか、その工法に関する論文を読み漁り、チーム全体で勉強しました。
そのようなこともあり、日本では、この工法に関しては我々が一番理解し、精通しているとの思いが強くなりました。自分たちの技術力への過信から来る驕りがチームに蔓延していました。
そのようなこともあり、視察に来た技術者からいろいろアドバイスを受けましたが、そのようなことはすでに検討済みといった態度で、真剣にそのアドバイスを考慮することはありませんでした。
設計が完成し、構造物の構築が終わり、構造物の運用に入ると、いくつかの個所でトラブルが発生しました。そのトラブル個所が、以前、現場を訪れた人からアドバイスを受けた場所であったことから、設計検討していたときの我々の傲慢な姿勢を強く反省することとなりました。
驕りから、人の貴重なアドバイスをきけなくなってしまっていたことに気づいた経験でした。
その後、いくつかの設計に携わることがありましたが、このときの経験を教訓として、常に、謙虚な姿勢で、人の話を聞き、自然に対してもその怖さをよく頭に入れるよう、留意しました。
驕りを戒める方策 2点
戦いに臨み、勝利を挙げ、絶頂期にいるときに驕らず、その先を見据えて努力することの難しさを紹介しました。
では、そのような絶頂期に至ったときにも、驕ることなく、次に備えるためにはどうしたらよいのでしょうか。
その方法として2点大切なことがあると思います。
一点目が、自分が自信過剰になっていることに気づくこと。そして、二点目が、高い目標を掲げ、その途中で満足せず努力を継続することです。
(1) 自信過剰であることに気づく
私の経験談に書きましたが、我々が自信過剰になっていたときに、ある上司から「お前、少々いい気になっているんじゃないか。そんなことでは、ろくな技術者にはならない。もっと自然に対して謙虚になれ」と指摘されました。
その後にトラブルを抱えたこともあり、驕りに気づくためには、自然に対しても、人に対しても謙虚であることが大切と思います。
(2) 高い目標を掲げ努力を継続する
ワシントンDCで、柔道家山下泰裕氏にお会いしたときの言葉がよい参考になります。
山下氏に対し、「一 流の選手は、いくつも実績を上げ、もうこれでよいと思うことはないのか」という質問が出ました。そのときの氏の答えです。
「我々が行き着きたいところは自分が描いた遙かに 高い理想の姿。その理想に向けて自分を鍛錬していく過程において、途中の実績は関係ない。
後ろを振り向かず、前だけを見て生きてきた。途中で休んで、周りを見、水を飲むくらいのことは必要だが、腰を下ろして、良くやった。“よっこいしょ”と言った瞬 間に、引退の時が来ている気がする。」「人は、我々のこれまでを見て、凄い凄いと言ってくれるが、我々の目標は先にあるだけ。後ろを見ることはない」
まとめ
戦いに勝利する、もしくは、今まで人が挑戦していないことに取り組み、ある程度その成果が見えたようなとき、人は、どうしても、喜びから傲慢になってしまうようです。
そのときに、その傲慢さを振り切り、さらに一段高いところを目指すうえで、柔道家山下氏は、一つの達成は、自分が描く理想の姿への一歩に過ぎないという姿勢をいつも持ち続けてることの重要さを話していました。
私も、建設現場での経験から、つねに謙虚な姿勢で、人、自然に相対することが大切であることを学びました。