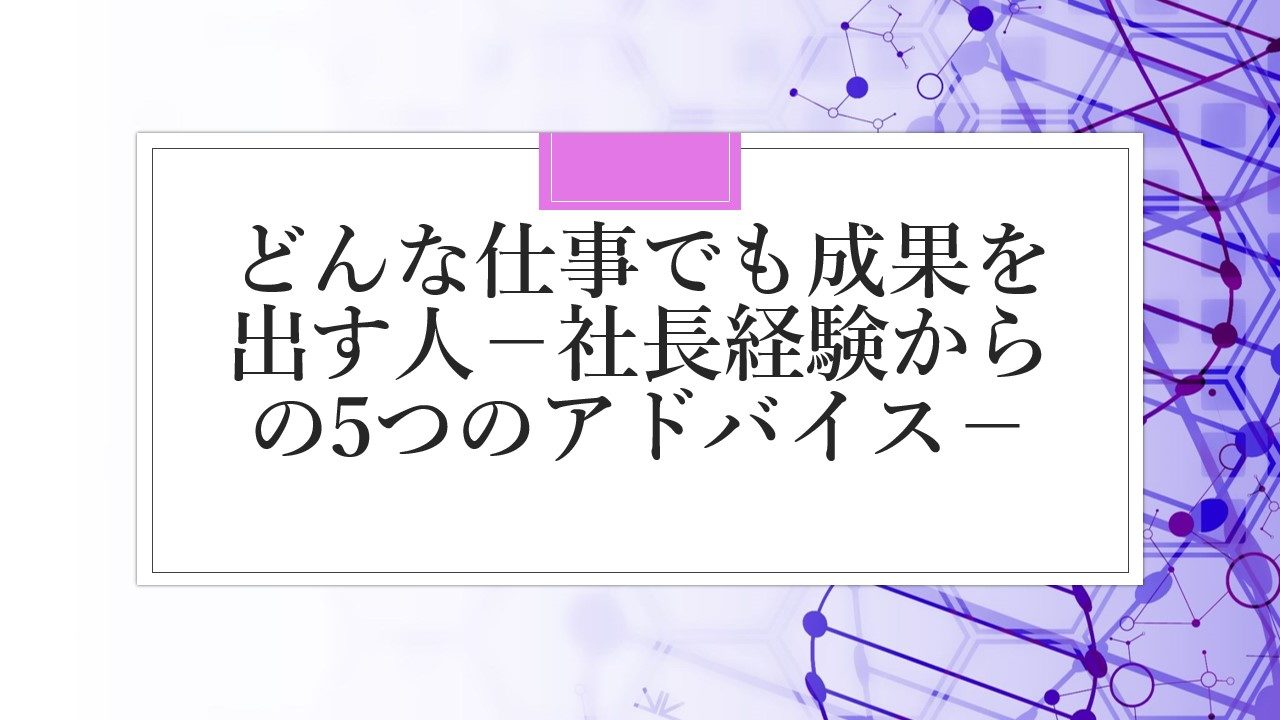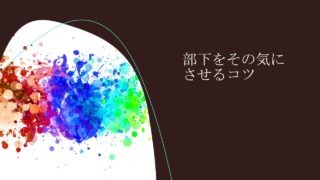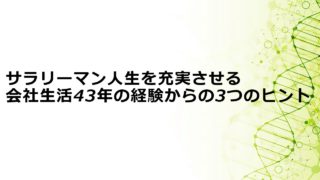長年、会社生活を送っていて気が付くことに、どの部署に異動しても成果を出す人がいれば、そうでない人がいる、ということがあります。
作家、宮本輝氏も、その作品の中で、ある会社の社長が、自分の部下を見て、同様なことを感じている話を書いています。
では、どうしてこのような差が出てきてしまうのでしょうか。
会社の担当から、最後は社長を務め、多くの人と付き合った経験から、ひとつの仕事を成し遂げるまでに、その人がどのような訓練をしてきたかが大きく影響されるようです。
また、アスリートとして一流の成績を残し、その後、組織のトップとなり、立派な成果を上げた人たちの話を聞くと、そこにもヒントがあるようです。
ここでは、会社生活でどのような力を磨くことで、どんな仕事でも成果が出せるようになるか、私の経験と一流アスリートの言葉から紹介します。
一つのことがちゃんとできるやつ
小説「草原の椅子」は、阪神淡路大震災後の阪神地域に暮らす50歳のサラリーマンで、妻と離婚し、娘と暮らす遠間憲太郎を主人公にしています。
小説は2部に分かれており、ここで紹介するのは上巻です。
主人公の遠間は、震災の衝撃がまだ残っている中で、パキスタンの桃源郷といわれているフンザを訪れました。
そこで出会った長老から遠間に告げられた、「潔癖」「淫蕩」「使命」の3つの言葉が、その後の遠間の人生に何らかの影響をおよぼしながら話は進んでいきます。
上巻では、会社の仕事で知り合ったカメラ販売店の社長、富樫重蔵との仕事を越えた友情のもと、50歳という年を迎えた二人の男性に降りかかる、仕事や女性問題に関わる話題を中心に話が展開していきます。
ここで紹介する一節は、交通事故で下半身が不随となった遠間の部下の再就職を、親友である富樫に依頼している場面です。
その部下は営業マンとして、遠間が、その能力と実績そして人間的な魅力を高く評価していましたが、下半身に問題が生じた部下に合う仕事があるか、遠間が懸念していました。
再就職の当てがない中、富樫に相談したときに富樫がかけた言葉です。
(遠間)「堂本はね、得意先の人たちに好かれるんだよ。この二、三年は、カラー・コピー機の販売が仕事の主だったんだけど、小さなトラブルだろうと何だろうと、少しでも苦情や問題が起こると、必ず足を運んで、面倒がらずに最後まで処理する。
問題がなくても、機械の調子はどうですかって、得意先をこまめに廻るんだ。だから、ライバル社がどんな新製品を出しても、性能にたいした差がないのなら、堂本くんから買ってやろうってことになる。
たしかに、労を惜しまず体を動かして仕事をするってのが彼のやり方だったから、車椅子の生活になって、自分に何ができるかって、とりわけ不安なんだと思うよ」
砂糖もミルクも入れずにコーヒーを飲みながら、
(富樫)「ひとつのことが、ちゃんとできるやつは、ほかのことも、ちゃんとできるんや。つまり、その逆のケースは、ほとんどないっちゅうことや。ひとつのことができんやつは、ほかのことをさせても、結局、あかんちゅう場合が多い」
と富樫は言った。
どこの組織でもあり得るケースを、富樫は明確に述べています。
それでは、どんな仕事についても成果を出す人材になるためには、どうしたらよいのでしょうか。
その解決策として、以下の5つの点が参考になると思います。
- 核心を突く目を養う
- 忍耐力を養う
- 決断力をつける
- 前向きな姿勢を保つ
- 謙虚な姿勢を保つ
核心を突く目を養う
仕事に従事しているときに、そこにどのような問題が潜んでいるかを見極める力(核心を突く目)が備わっていることで、早い段階でその問題の解決策を考え、手順を考えて仕事を進めることができます。
このことは、どのような仕事にも当てはまることだと思います。
この能力を有する人が、今まで関与していなかった仕事に従事するようになっても、迅速に処理し、成果を出すことができた事例を、私は多くの職場で見てきました。
前のブログでも書きましたが、プロ野球の王貞治氏は、有名な一本足打法を生み出す練習の中で、この核心を突く目を養うことが大切であることを、技術を磨くうえで大切なことの一つとして挙げています。
忍耐力を養う
私は、土木構造物の建設現場での10数年間で、多くのトラブルに遭遇し、上司、仲間とともに、そのトラブルを解決した経験があります。
あるトラブルでは、最初に考えた解決策が功を奏さず、何回かやり直しをすることで、最終的にその構造物を完成させることができました。
幾度となくあきらめる気持ちがわいてきましたが、そのたびに、上司、仲間の支援を得て、トラブルの解決に結びつけることができ、このときに、忍耐する能力を養うことができたのだと思っています。
その後、会社の経営幹部となり、経営に参画することになりましたが、会社を取り巻く環境が時々刻々と変化する中で、じっくり問題の本質を見つめることができたのも、この忍耐力のお陰であると思っています。
前向きな姿勢
どんな職場に移っても、成果を出す人に共通している特質として、常に前向きに物事を考える習性を身につけていることがあげられます。
難しい仕事に出会った際にも、そこに存在する問題を何とか見出そうとする力も、この前向きな姿勢から生み出されてくるのでは、と思っています。
職場が変わることで、このように難しい問題に遭遇する機会が増えます。しかし、このように前向きに物事を処理しようとする人であれば、最初の頃は時間がかかるかもしれませんが、きちっとした成果を上げることが可能になると思います。
柔道家、山下泰裕氏は、1980年のモスクワオリンピックを日本が出場辞退したことで、そのオリンピックに参加できませんでした。
さらに不運は重なり、全日本選手権で大けがをしてしまい、二重苦を負う山下選手という評判が立ちました。
しかし、そのような状況にあっても、山下選手は、病院のベッドで「よく頑張ってきた、思うようにいかないかもしれないけれど、体と心を休ませなさい。もう一度じっくり新しい一歩を歩き始めなさい、という言葉が聞こえてきた」と語ったそうです。
このように、一流アスリートは、困難に出会っても、常にその事態を前向きにとらえるような特質を持っているようです。
我々サラリーマンも、今までに経験したことのない職場に異動した際にも、前向きに取り組むことで、その職場での成果をあげられるのだと思います。
謙虚な姿勢
前向きな姿勢と同様に、成果を出す人に共通な特質として、謙虚な姿勢が常にみられることです。
逆に、自分が、自分がといって、しゃしゃり出てくる人は、どんな職場でもなかなか成果を出すことが難しいような気がしています。
謙虚であることで自分の弱点をしっかり見極めることができ、そのことが仕事に向かう上で有効であるのでは、と思います。
初めての仕事について、自分の能力でできること、仲間の支援をどうしても得なければならないことにすぐ気が付くことができるのが、この謙虚でいることの特質のすぐれた点だと思っています。
何を自分で処理し、何を仲間に助けてもらうかが明確になれば、問題の対処方策が明らかとなり、その方策を進めていくことで、成果を出すことができるようになるのだと思います。
決断力をつける
担当から経営者まで、そのレベルに差はあるものの、どんな仕事に従事していても、どこかで問題を処理するために決断をしなければならないときが来ます。
この決断すべきときに、逡巡してしまうか、失敗を覚悟してでも自ら決断できるかが、その仕事で成果を出すことができるか否かの分かれ道になると思います。
この決断力は、どんな仕事にでもついて回るものであり、この能力の有り、無しが仕事をちゃんとできる人かどうか、評価される一つの指標であると思います。
まとめ
どんな仕事でも成果を出すために必要な能力として、① 核心を突く目を養う、② 忍耐力を養う、③ 決断力をつける、④ 前向きな姿勢を保つ、⑤ 謙虚な姿勢を保つ
の5点を紹介しました。
いずれも、すぐに身につく能力ではないと思いますが、自分の経験から、常に意識して行動することで、養われる能力であると思っています。