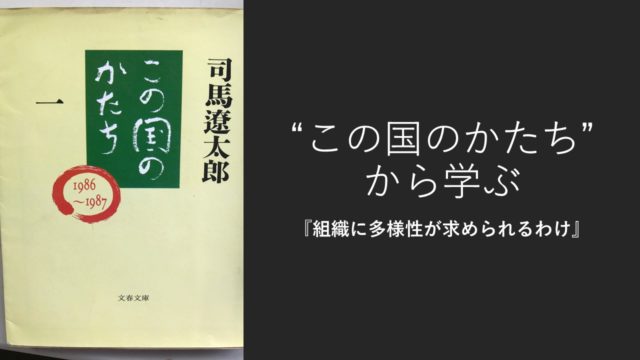組織が活性化しない原因は幾つかあると思いますが、セクショナリズムはそのうちの大きな原因のひとつです。
自分の部署を守りたいといった意味で、他の部署との間組織が大きくなればなるほど、部門の壁が高くなる現象、セクショナリズムが強くなり、仕事の効率が落ちてきます。
自分の部署だけで問題を解決できるうちは、セクショナリズムはそれほど大きな影響を与えないことから、その悪さは見逃されることが多いようです。
しかし、自分の部署だけでは到底解決出来ない問題に遭遇すると、部署間の情報が共有されなかったり、ひどい場合には、問題解決を遅らせるような手立てが講じようとしたりするなど、セクショナリズムの悪さが露呈します。
セクショナリズムがはびこることで具体的にどのような弊害が生じるのでしょうか。
今野敏氏はその著書で、警察という組織のなかでのセクショナリズムを取り上げ、その弊害と対応策について書き記しています。
私も、社長を経験したときに、部門間の縦割りがひどく、大きく事業を変えていこうとするときの障害となり、その解消のため多くの労力を費やしました。
今回は、今野敏氏の小説と私の会社経営の経験から「セクショナリズムの弊害と対策」について紹介します。
警察内のセクショナリズムの弊害
小説「清明」は、東京の町田市で起きた中国人が絡む殺人事件の捜査がテーマです。捜査に絡む組織上の問題などを、主人公である竜崎神奈川県警刑事部長が解決し、犯人をあぶりだしていきます。
被疑者が中国人である可能性が強まり、捜査本部に詰める警視庁の田端課長が、警視庁公安部にも一報入れておくことを提案します。
一方で、公安部と刑事部とは、その捜査方針の違いから、これまでも協力関係を築くことが難しいことが知られており、刑事部の中には、公安部との協力について懐疑的な人がいました。
しかし、竜崎部長は、むしろ中国の情報を多く持つ公安部に協力を依頼するほうが得策と考え、協力体制を取ることを指示しました。
そのような中、協力体制を築くことはなかなかに難しいものになりつつありましたが、竜崎部長は、刑事部と公安部との連携について強く主張するのでした。
(田端課長)「犯行の動機は奥が深そうですね。念のため、外二に声をかけておこうと思いますが——」
中国担当は公安部外事二課だ。そこから情報を得ようというのだろう。
(竜崎部長)「公安なら豊富に情報をもっている。協力体制を作ってくれ」
「やってみます」
公安は一筋縄ではいかない。こちらからの情報だけを吸い上げ、自分たちのほうから情報提供をしない、などという例がざらにある。
警察すべてが国のため国民のために働いていることは疑いのない事実だ。だが、それが当たり前すぎて、つい忘れてしまいがちだ。
根幹を忘れると、枝葉にこだわるようになる。つまり、セクショナリズムや極端な秘密主義だ。いずれも自分が属しているコミュニティーを守ろうとする低次元の欲求から来ているのだと、竜崎は思っている。
———-
県と県とが対立するなら、自分たちは同じ日本国民だということを意識すべきなんだ。
同じことが職場でも起きる。
警視庁内部でも、刑事部と公安部が対立することがある。全国の公安は事実上警察庁の警備企画課が統括しているので、地方警察の刑事部と並べて考えるのは難しいし、彼らはそれなりのプライドをもっている。だが、同じ日本の警察なのだ。争う理由はない。
(今野 敏著 清明)
セクショナリズムを打破する対策
この項も、「清明」からの引用です。
町田市での殺人事件の捜査本部は、警視庁主導で体制がつくられ、町田市が神奈川県と近接していることから神奈川県警も協力することになりました。
警視庁の伊丹刑事部長が捜査本部長となり、神奈川県警の竜崎刑事部長も本部に詰めることになりました。
伊丹捜査本部長が席を外している中で、捜査を進展させるため、ある判断を本部として下す必要が生じました。
本部に詰め、現場の指揮を任されている警視庁の岩井管理官が、竜崎部長に判断を求めました。
いつもは、張り合っている警視庁と神奈川県警ですが、そのセクショナリズムを打破する行動を竜崎部長がとりました。
岩井管理官が竜崎に言った。
「すぐに被害者の氏名を捜査員たちに流します」
竜崎はうなずいた。
「そうしてくれ」
岩井管理官にとっては、警視庁も神奈川県警も関係ないようだ。とにかく幹部席に座っている一番偉い人が竜崎だ。だから岩井管理官は竜崎に判断を仰いだのだ。
竜崎はその状況を受け入れていた。—–というより、当たり前のことだと思っていた。どこの所属であろうが、そんなことは問題ではない。
その場で判断を下せるものが指示を出せばいい。警察という組織の性格上、命令系統は守られなければならないが、そんなことは問題ではない。
(今野 敏著 清明)
いつもは、張り合い、セクショナリズムから良好な関係作りが出来なかった、警視庁刑事部と神奈川県警刑事部は、竜崎部長が示す“犯人を逮捕することが警察の使命”、という竜崎部長の大義のもと、所属の壁を取り払って捜査を進めていくのでした。
なぜセクショナリズムが蔓延してしまったのか
私が、ある土木、建築関係のコンサルタント会社の社長になったときの経験です。
私が社長になる前の仕事の受注状況は、特定の会社からの受注が70%程度ありました。また、その会社の各部門と自社の各部門とは、それぞれに仕事を通じた強力な関係があり、ある部門から発注される仕事は、そこと関係のある部署だけでの対応が可能でした。
このため、会社内では、他部門の協力を得ることはめったになく、単独で仕事を進めることが続きました。
また、部門ごとに売り上げ、利益を競争することもあったため、他部門に関係のありそうな仕事の話があっても、進んで関係部門にその情報を連絡することがありませんでした。
このようなことで、部門間の縦割りの壁、セクショナリズムが強い会社となっていました。
セクショナリズムを打破するためとった対策
私がその会社の社長になったとき、それまで70%近い仕事を受注していた会社からの受注が、将来落ち込むことが確実視されていました。
このため、特定会社以外に販路を広げる必要があり、その会社以外にお客様を見出し、商材を売っていくことを早急に軌道に乗せる必要がありました。
この変革を進めるうえで、一番に問題となったのが、各部門の縦割りの壁でした。
お客様からのニーズが多様化する中、特定の部門だけでは到底対応することが出来ないことがはっきりしていたことから、部門間の連携を図るため、この縦割りの壁を打破することが大きな経営課題でした。
このため、社長就任直後から物理的な面と精神的な面での方策を遂行しました。
物理的な方策としては、各部門が別々のフロアーで仕事をしていたものを、事務所移転を契機に、社員全員が同じフロアーで仕事ができるようにワンフロアー化を図りました。
これにより、社員の皆が人の顔を見て仕事ができるようになり、社内のコミュニケーションが活発化しました。
また、精神的な方策としては、「なぜ縦割りの組織では外の市場に売っていくことが出来ないか」を繰り返し発信し、社員とも直接会い対話することを続けました。
この対話を繰り返すことで、当初、縦割りの世界から抜け出せずいた社員も、他部門と協力して仕事をすることの必要性を理解してくれるようになりました。
2年もたつと、縦割りの弊害が意識され、他部門との協力体制も始まり、徐々に、特定の会社以外からも仕事受注することが出来るようになりました。
まとめ
大きく会社を変えようとする中で、セクショナリズム、もしくは縦割り社会というものは、事業を広げる、問題を解決するときなどには阻害要因となるものであることがよく分かりました。
今野敏氏も書いているとおり、このセクショナリズムは、長い間のその組織のありようから根付いてしまったもので、なかなかに打破することが難しい問題であることは確かだと思います。
その組織のトップが、セクショナリズムの悪さを意識し、打破することを宣言すること、そして、壁の打破に向けて具合的な対策を講じることが大切です。
さらに、働く一人一人が、セクショナリズムの悪さを意識し、自ら打破することに目覚める必要があると思っています。