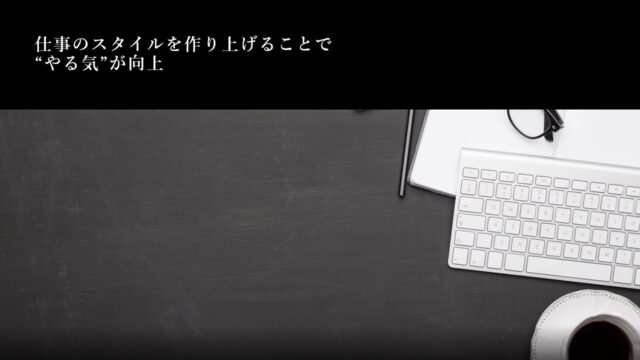難しい仕事に直面したとき、さらには、新しい事業を成功に導こうとしたとき、いろいろ考えてしまい、最初の一歩がなかなか踏み出せないことがよくあります。
前に出ることで失敗するではと、心配したり、やりだす前の準備で疲れてしまったりして、一歩踏み出すことためらわせるのだと思います。
こんなとき、思い切って「とりあえずやってみる」ことが重要なことと思っています。
作家、司馬遼太郎氏は、その作品の中で、この「とりあえずやってみる」の大切さを書いています。そこでは、主人公に「完璧を目指さず、まずは八分で進め、そこから新たな課題を見つけることが大切」と言わせています。
私も、新しい事業に挑戦したときに、完ぺきを目指し、またなれない業務から、一歩を踏み出せない社員に対し、まずはやってみることで活路を開くことを指導しました。その結果、数年を経て事業を拡大することが出来ました。
今回は、一歩踏み出すためにはどうしたらよいかといった点について、司馬氏の作品と私の社長としての経験から紹介します。
まず八分をめざし、とりあえずやることが大切
小説「花神」の主人公は、明治時代に我が国の近代兵制を築いた大村益次郎です。
まだ村田蔵六と称した時代、緒方洪庵塾で蘭学を学び、その後、生国である周防鋳銭司村(現山口県山口市)の実家の医家を継いでいました。
医家になったものの、その性格から医者であることに馴染めずにいたところ、蔵六の蘭学の能力の高さを知った、当時の4賢侯の一人である第八代宇和島藩主、伊達宗城に招聘されました。
宇和島藩では藩主の強い意向もあり以前から蘭学に熱心でした。
伊達宗城が江戸湾警備の任にあたっていたときにペリーの来航があり、その蒸気船の姿を見た宗城は、自らの藩でその蒸気船を作ることを決心しました。
宇和島藩には、蒸気船を作る技術を持った人材はおらず、外にその責任者を求めることになり、緒方洪庵の推挙を経て村田蔵六が宇和島に行くことになりました。
ここで紹介する一節は、蔵六が宇和島で蒸気船づくりに着手し、蒸気船の知見を得るために長崎に出向き、滞在していたときの話です。
昔からの知り合いである蘭医、奥山から「蒸気船なんかできるのか」と問われたときの蔵六の返事です。
(蘭医奥山)「ほほう。黒船の船体をつくるのか」
と、奥山はおどろき、それは三百年来の壮挙だ。いやまったく赤穂浪士の討入りにまさる快挙だ、などとさかんに感心癖を発揮した。
「しかしできるのかえ、おぬし一人で」
と、奥山はそれがふしぎでならないらしい。蔵六は日本の伝馬船の作り方さえ知らないはずではないか。
「まあ、八分どおり出来ましょう」
蔵六は、妙なことをいった。
銅座町から、イネ(シーボルトの娘)がときどき訪ねてくる。このイネも、奥山同様の質問をした。蔵六はおなじように答えると、
「まあ、八分どおり?」
と、イネはオウム返しにつぶやき、爆(はじ)けるように笑いだした。
――――――――――
「沈みはしません。しかし強い風が吹くとホバシラが倒れましょう」
「まあこわい」
「ホバシラの据え方にいま一つ不明のところがあって、このように長崎にきています」
――――――――――
「しかし八分どおりでいいのです」
と、蔵六はいった。
蔵六にいわせると、まず作りあげてみることであった。作ってうかべて動かしてみれば欠陥がぞろぞろ出てくるであろう。その欠陥を手直しする過程において、宇和島藩の造船能力が養われるのである。
まずやることなのだ、というのが、蔵六の思想であった。
(司馬遼太郎著 花神(上巻))
この後、蔵六は、蒸気機関をつくった嘉造と協力し、日本最初の純国産蒸気船を作り上げました。
難題を多く抱える中、まず作りあげるという蔵六の強い意志が、このような成果を上げることになったのでした。
市場拡大のためにまずお客様のところへ
私が、土木建築関係の設計コンサルティングを扱う、ある企業の子会社の社長になったときのことです。
私の会社は、親会社の設計部門を担っていたこともあり、仕事は親会社から受注することがほとんどで、会社の業績は、親会社からの発注の多寡で決まる構造となっていました。
このため、特に会社として成長を目指す必要もない状況が続いていました。
私がその会社の社長になる直前に、親会社に大きな経営上の変化があり、仕事の受注が今までのように期待できず、このままでは会社は経営を縮小していくしかない状況でした。
このため、私が社長になったときに親会社だけをお客様とするのではなく、親会社以外の企業も顧客対象とすることで、市場を拡大することを考えました。
ほとんど、親会社以外の顧客に商売をしたことがない会社であったため、どのように技術的な商材を売っていくかが大きな課題でした。
実際、社員からは「あの企業には、もう他のコンサルタントがついているから」などと一歩踏み出すことに躊躇する意見が多く出ました。
そこで、まずは会社の技術を買ってくれそうな顧客のところへ伺い、我々の技術を紹介することから始めることを社員に指示を出しました。
幸いなことに、親会社から仕事を受けていたことと、親会社と共同で技術開発を進めていたこともあり、技術的にはわが国でもハイレベルの商材も結構ありました。
そのようなことから、それらの商材をどうやってお客様に知ってもらうかかが、最初の一歩でした。
まずは、親会社と関連する会社をターゲットに、技術の売り込みを始めました。
今まで、親会社以外の顧客とのおつきあいが少なかったこともあり、なかなかに営業らしきことが出来ず、一歩を踏み出せない状況でした。
しかし、完ぺきを目指さず、まずは会社を知ってもらうこと、そして顧客のニーズを聞き出すことから営業を始めました。
しばらくすると、いくつかの顧客から、我々が持つ技術に興味を持ってもらえるようになりました。さらに、技術の使用実績を説明する中で、顧客のニーズを明確につかめるようになり、そのニーズに対応することで、わが社に仕事を発注してもらえるようになりました。
そのようなことを繰り返しているうちに、親会社以外の顧客との付き合いも増え、徐々に、受注が増えていきました。
そうこうするうちに3年が経ち、年度の受注量の半分以上は、親会社以外の顧客からのものとなりました。
最初に始めるときに、完ぺきを目指していたならば、慣れない社員も委縮し、一歩を踏み出せず、成果が出なかったかもしれません。しかし、まずは顧客にあたってみることを進めたことで、活路が開けた経験でした。
まとめ
今までと違った事業に出ようとしたときとか、大きな課題を担わされたとき、どうしても、最初の一歩を踏み出せないことがあります。
これは、何もしないうちに完ぺきな成果を期待してしまい、どのように手を出していくか、見当がつかなくなってしまうからであると、私は考えています。
もっと気楽に、まずは、その目標に向けて、考えられる手段で一歩踏み出してしまうことが大切だと思っています。そして、村田蔵六が言うとおり、完璧でなくとも八分で良しとする意識を持つことが大切なことと思います。
一歩踏み出してみると、その先がまた見えてくるようになり、新たな手立てが考えられるようになります。そして、そのようなことを繰り返すうち、最初に設定した目標まで到達が可能なるものだと思います。